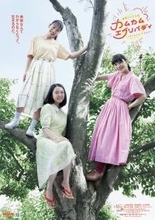この年明けよりNHK大河ドラマの新シリーズ「平清盛」が始まっている。その主人公はタイトルどおり平安時代末期の武将だ。
ここでいうモチベーションとは、戦国時代後半の武将たちにおける“天下統一”、幕末の志士たちにおける“倒幕”といった類いのものだ。それが清盛の場合、すぐには思いつかない。保元の乱(1156年)や平治の乱(1159年)を経て、1167年に当時の政治のトップである太政大臣にまで登りつめた清盛は、娘を天皇家に嫁がせるなどして積極的に摂関制という既存の体制のなかへ入りこもうとした。そのため、清盛については「武士として独自の政権を確立したわけではない」といった見方が学界でも長らく根強かったようだ。
ただしあれこれと調べてみると、最近では、清盛は福原(現在の神戸市内)に新都と港の建設を推し進め、これに加えて厳島神社や九州の大宰府を拠点とした西国政権の確立をめざしていたとする説が歴史学の趨勢らしい。與那覇潤『中国化する日本 日中「文明の衝突」一千年史』によれば、清盛がめざしたのは、宋との貿易を通じて日本国内に外貨を大量に流入させ、農業と物々交換に立脚した古代経済を一新し、かつ荘園制に立脚した既存の貴族から実権を奪い取ることだったという。これに危機感を抱いたのが、国際競争に適した主要産品を持たない源氏をはじめとする東国の武士たちである。彼らはやがて、荘園経済で利益を得ていた貴族や寺社勢力と手を組むことで平家を滅亡に追いこんだ。これこそ源平合戦の実態であった、というわけである。
■40年前の大河で清盛はどう描かれた?
さて、今回の大河ドラマ「平清盛」について……と行きたいところだけれども、このレビューではあえて40年前に放映された大河ドラマ「新・平家物語」をとりあげてみたい。
「新・平家物語」の原作は昭和の大衆小説の巨匠・吉川英治の同名小説だ。大河ドラマでとりあげるにあたっては直木賞作家の平岩弓枝が脚色している。平岩は60年代から70年代にかけて、小説と並行して「肝っ玉母さん」「ありがとう」などといったホームドラマの脚本を手がけ人気作家となっていた。大河ドラマへの平岩の起用には、「平家という大家族の興亡劇にホームドラマの要素を盛り込み、清盛を取り巻く女性たちもクローズアップしよう」という意図があったという。そこには主婦層を取りこもうというねらいがあったことはいうまでもない(鈴木嘉一『大河ドラマの50年』)。
大河版「新・平家」では主役の平清盛を仲代達矢が演じたほか、若尾文子、山崎努、木村功、中村玉緒、中村勘三郎(17代目)、新珠三千代、滝沢修、水谷八重子(初代)、加東大介、森雅之、岡田英次、緒形拳、藤田まこと、北大路欣也、田村正和などなど、歌舞伎、新劇、映画など各界から豪華俳優陣がそろえられた。ちなみに出演当時の仲代達矢は40歳。「平清盛」主演の松山ケンイチは今年27歳だから、ひと回り以上も年上ということになる。
冨田勲作曲の重厚なテーマ音楽によるオープニングタイトルが終わると、厳島神社に清盛以下平家一門が集ったシーンからドラマが始まる。
ナレーションといえば、保元の乱で敗れた藤原頼長(成田三樹夫)が、重傷を負いながら輿に乗って父・忠実のもとにたどり着くも、家に入るのを許されないまま息絶える場面での「輿はそのまま棺となった」というフレーズにはしびれた。同じ敗者でも、小沢栄太郎演じる信西入道の最期のシーンは滑稽ですらある。後白河天皇(滝沢修)の側近として権力を振るった信西だが、藤原信頼(亀石征一郎)や源義朝(木村功)たちの反乱(平治の乱)を受けて都の外れへ逃走する。その途上、信西は追っ手から姿をくらまそうと従者たちに穴を掘らせ身を隠すものの、結局見つかり殺されてしまう。穴のなかで鼻の孔に栓をして、外に突き出した竹の管をくわえる信西の姿はいかにもマヌケだ。
映画やテレビドラマで何度も悪役を演じてきた成田と小沢だけに、ヒールとして設定された頼長と信西も役にハマっている。いま、こういう役者ってほとんどいないよなあ……と思わざるをえないのが残念なところだが。ただ、史実に照らせば、頼長も信西も教養あふるる才人でありかなりの切れ者であったようだ。
さて、義朝らが反乱を起こしたとき、清盛は一族郎党を連れて熊野詣に出かけていた。反乱発生を知った清盛は、信西から優遇を受けていたことからすぐさま京へ引き返し、義朝軍を討つ。雪の降りしきる洛中を、赤旗を掲げて平氏の軍が進む様子は、さながら華麗な絵巻物を見るようだ。平治の乱では京の市中が戦場となり、「平治物語絵巻」でも描かれているように、御所や住居などの小さな門を挟んで激しい戦いが繰り広げられた。こうしたせせこましくも絢爛な合戦シーンはロケではなく、たっぷりと予算をかけた大道具をつくったスタジオでの撮影こそふさわしいと思わせるに十分だ。
平治の乱で平氏の軍勢に敗北を喫した義朝の一門は都落ちし、義朝は逃亡先で殺害され、遺児となった源頼朝は平氏に捕らえられる。まだ13歳だった頼朝について義母・池禅尼(初代・水谷八重子)から助命するよう口添えされた清盛が、頼朝と二人きりで話をするシーンは、総集編「上ノ巻」の山場の一つだ。子役演じる頼朝の受け答えはいかにも利発で、つい萌えてしまう。この浅田真央にちょい似の子役は誰? と思って調べたら、岡村清太郎、現在は江戸浄瑠璃清元節の家元である7代目清元延寿太夫だという。
続く総集編「下ノ巻」では、平治の乱ののち権力を二分するにいたった後白河法皇と清盛が、お互いを利用しつつせめぎあう様子が描かれる。法皇を演じるのが主演の仲代より26歳も年上で新劇界の大先輩でもある滝沢修だけに、法皇と清盛はまるで父子の関係にもとれる。
鹿ケ谷事件ののち清盛はクーデターにより法皇から権力を奪取するのだが、法皇は源氏をはじめ東国の武士らに平氏討伐を呼びかける。各地で反・平氏勢力が挙兵するなかで、清盛は福原に都を移すも、すぐに京都に戻る。ただ、総集編を観たかぎり、清盛がなぜそこまで福原にこだわったのかよくわからない(新都と港=大輪田泊の建設に長らく力を注いでいたことは一応は説明されているとはいえ)。このあたりはダイジェストということに加え、冒頭に書いたような清盛に関する“わかりにくさ”も原因しているのかもしれない。ともあれ、一族に脅威が迫るなかこの世に大きな未練を残しつつ清盛が息を引き取るシーンは、仲代の熱演により劇的なものとなっている。ここらへんのいい意味で芝居がかった演技はまさに新劇俳優の真骨頂という感じがした。
清盛が亡くなってからはさすがに駆け足という印象はさすがに否めない。
■カラーテレビ時代の大河ドラマ
「新・平家物語」が放映される前年(1971年)、NHK総合テレビの全番組がカラー化され、この年にはカラーテレビを所有する世帯が50%を超えた。先ほど同作を絵巻物にたとえたが、当時のNHKには、カラーテレビにふさわしい華やかな歴史絵巻を描こうというもくろみもきっとあったに違いない。
テレビはまた、それまで娯楽の王者だった映画からその座を完全に奪い取った。映画大手5社(一時6社)は1950年代にいわゆる「五社協定」を取り交わし、専属俳優のテレビ出演を制限するなどしてきた。NHK大河ドラマは1963年の「花の生涯」をもって始まるが、この当時にはまだ「五社協定」は厳然と存在し、映画俳優の出演依頼には苦労したようだ。それが10作目の「新・平家物語」では、大映の看板女優であった若尾文子や中村玉緒のほか、主演の仲代達矢をはじめ山崎努、木村功と新劇出身ながら世間的には黒澤明監督の映画などで名を知られるようになった俳優たちが多数顔をそろえた。ここには映画産業の衰退も深くかかわっているはずである。じつに同作放映の前年、大映が倒産したほか映画各社は方向転換や組織の再編を余儀なくされ、「五社協定」は事実上崩壊している。
かつて銀幕を飾ったスターたちを出演陣にそろえたNHKの「新・平家物語」は、名実ともにメディアの王座についたテレビの“勝利宣言”でもあったように思われてならない。もっとも、「おごれる人も久しからず」ではないけれど、40年を経てテレビもかつての映画同様に大きな曲がり角に立たされている。