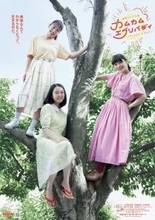夢から目を覚ました主人公、桐山零。
起き上がる。
殺風景な部屋。
窓を開け、外を観る。川。

「アニメはキャラクターだ。まずキャラクターの特徴をアクションで観せろ」
アニメ制作の授業や本は、そう教える。
だから、たいていのアニメは、走ったり、戦ったり、叫んだりする。
なのに、いきなり目覚めて、立ち上がって、窓を開ける。
日常の風景だ。
にもかかわらず目が離せない。
服を着替えて、外へ出て、歩く。
自動販売機で水を買い、将棋会館へ。
対局が始まろうとしている。
「……元気だったか? 零」
零は喋らない。
対局。
回想シーンがはさみこまれる。
だが本当に1ショット1ショットで、説明らしい説明は無い。
「負けました」
相手が頭を下げる。
「急に出ていって…歩も香子も心配してるぞ……」
立ち上がる。去っていく。
零はひとり正座している。
ここで、初めて主人公が喋る。
「うそだ」
と独りつぶやく。
9分だ。
9分間、主人公が喋ることも無く、わかりやすい説明も無く、大きなアクションも無い。
だが、すごいものを観ている興奮に巻き込まれる。
いや、「だが」じゃないのか。
「アニメはこうあるべき」という制約よりも、原作をどうアニメにするのかを誠実に考え抜いたことが判るからだ。
もちろんこれは原作をまったく同じようになぞるということではない。
たとえば、水の演出が繰り返される。
排水口に流れ込む水。
一瞬はさみこまれる水疱。
窓から入ってくる光を受けるウォーターサーバー。
鉄柵や橋の下に照る水の光。
水の描写が随所に入る。これらは、直接的には原作漫画では描かれていない。
昇っていく水の泡が、何度かはさみこまれる。
最初にはさみこまれた水の泡のシーンは、いきなりだ。
だから、見る側は、自分が、もしくは主人公が、水の中にいるように感じる。
ペットボトルの水が映された後の水の泡のアップさえも、その気分をリフレインさせる。
一枚の皮膜で現実と乖離している気持ちに観るものを導いていく。
日常をていねいにていねいにていねいに描く。
窓に映る起きる姿。
窓を開けて光がわっと入ってくる瞬間。
ズボンを2つ拾い上げ、片方をポイッと手放す。
机の上の眼鏡がつくる影。
零が歩く姿を正面から捉えたショット。
さらに、カメラがすっと寄って、逆光になり主人公に影が落ちる瞬間。
歩いているシーンも、移動が判りやすく描ける横からのショットではなく、正面向きで捉える。
電車に乗っている後のシーンに、ホームで電車を待っているシーンが入る。
説明的に描かれないので、ぼんやりと観ていると見逃すが、これは、東京駅で乗った主人公が、御茶ノ水で乗り換えている描写だ。
瞬間瞬間の緻密な描写と、その積み重ね。
簡単な方法に逃げるのではなく、必要な方法を必要なだけ使う。
絵に、おそろしいほどの情報量が詰め込まれている。
セリフや、アクションや、展開で、説明するのではない。
説明ではなく、瞬間瞬間を絵で手渡す。受け取った側が、それを組み立てる。
だから、目が離せなくなる。
何度も観たくなる。
主人公の声を演じる河西健吾はインタビューでこう語っている。
「お芝居以上のものがその無音に出てくると思うんですよ。ストーリーの空気感を感じることができる作品、楽しみにしてもらいたいですね」(NHKサイト「声優に聞いてみた3月のライオン」)
アニメーション制作は、シャフト。
監督は、新房昭之。
原作の漫画は、羽海野チカ。
アニメ『3月のライオン』NHKテレビ。
第2話、今日10月15日(土)午後11時放送。
第1話再放送、今日今日10月15日(土)午後5時05分放送。
必見。(米光一成)
参考→『3月のライオン』アニメ化とは、原作に忠実に、鮮烈に解釈して再構築すること