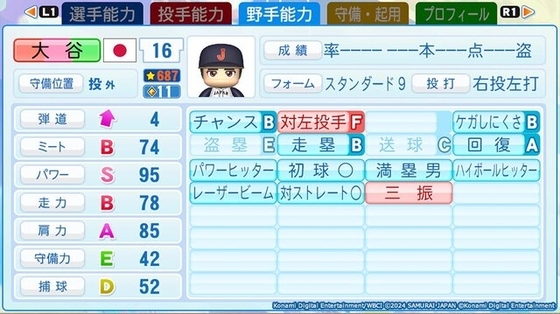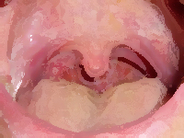ライター・編集者の飯田一史さんとSF・文芸評論家の藤田直哉さんによる、話題の作品をランダムに取り上げて時評する文化放談。前編記事に続いてアニメ映画『この世界の片隅に』について語り合います。
宿命を受け入れる映画なのか、そうではないのか
飯田 近いのに遠いというか、隣なのに別世界。そういうことの連続を描いている作品ですよね。原爆が落ちた広島の隣の呉、同じ「鈴」という名前を持ちお互い貧乏暮らしをしていたのにかたや遊郭で働いているりん、不発弾でとなりで亡くなる晴美。そういう人たちがいるなかで生きているからこそ彼女は「この世界の片隅」にいるのだと思っているという気がする。もしかしたら死んでいたのは自分だった、という場所に誰だって本当は生きていることを思い起こさせる。
藤田 そうですねぇ…… 生きるも死ぬも、どんな境遇に生きるのかも、ほんの紙一重だっていうのが、よく伝わってきますね。まったいらになった呉を見て、津波が来た地域を連想する人も多いでしょうね。
「復興」って書いてある看板も描かれていたと思う。
しかし、そのような偶然性、運命性、宿命性みたいなものを、こんなに受け入れすぎていいんだろうか。人間が抵抗する余地が全然ないようなものとして描いてしまっていいんだろうか。現実の社会問題や、階層の問題も、政治的行為としての戦争も、人間が作り出していることであるから、人間が解決できるものですけれどね。少なくとも、人間の力で解決しようとする人が出ることが自然なものではある。
飯田 「変えられる」けれども、程度がありますからね。
なんでも好き放題できるわけではない。
藤田 すずは、絵を描くことで、現実を「上書き」できる。今で言う拡張現実的な想像力を持っている。すずの描く絵が、時々、映画内の「字の文」に相当するところに使われる。……それが、アニメーションそのものの機能を自己言及しているようで面白かったものの、しかしそう考えると、悲惨な現実を美化して鈍感に生きることを肯定するアニメなのか、って思ってきて、なかなかにそこは悩ましいと思います。『君の名は。
』と同じ問題系ですけれど。
飯田 決して「悲惨な状況を甘受して生きろ」というメッセージではないと思ったけどね、すずたちの態度の描き方については。
今年はすごく貧困本が出た年だったけど、中村淳彦さんの『女子大生風俗嬢』を読んでもさ、たとえば慶應とかだと幼稚舎からきているボンボンもいれば、学費も生活費も自分で払って通っている地方の子とかもいて、後者は普通の時給のバイトを目いっぱい入れて生活しようとすると時間も体力も限界になってむしろ学生生活が破綻する、したがって風俗で働くほうが合理的な選択に映るという人もいるわけです。「なんで同じ大学の学生なのに向こうはぽんぽんお金使っていて、自分だけこうなんだろう」って思ったりする。制作陣が意図的かどうかはともかく、みんながまあまあお金がある時代じゃなくなった今の時代と、この映画で描かれているものとは、重なるところがあるなと僕は感じました。そういう「もうひとつの人生」を想像してしまうところに、すずの空想癖という設定が重なるなと。
藤田 「もうひとつの人生」があったかもしれないけど、吹っ切っている。同じように、近くにいる他者(性風俗で働いている人)のことも、よくわかっていない。それがよいのやら悪いのやら。
飯田 最後のほうでは「何も知らないままで生きられたらよかった」とすず自身言っているわけで、ずっとぼーっとしていたわけではない。鈍感なりに徐々に気づいていってはいる。
藤田 家とその周辺のことが重要で、あんまり社会とか国家とかに視線は向いていないですよね。
もし現在に生きていたら、日々生きるのに精一杯で、貧困とか格差の問題に目を向けたり、どうにかしようとしない人だってことになっちゃう。
飯田 あの環境にいたらそれはそうなるでしょう……教育が小学校止まりだし。メディアだってほとんどラジオしかないし。だからこそ「片隅」なんだろうし。
藤田 多分これ、主題と重なると思うんですけど、彼女は「運が良かった」んですよね。嫁いだ家がああだったからよかったし、旦那もああいう人だからよかった。
しかし、もしそれが違ったら…… たとえば、暴力を振るう亭主とかだったら、全然違う。
現実を書き換える想像力――二人の出会いは現実か虚構か
藤田 気になるのは、二人の出会いの部分(冒頭)でして。すずが作った「お話」の中の出来事なのか、現実なのか、曖昧になっています。あれ、どう解釈します?
解釈のひとつなので、あそこで、すずが、絵を描く力・想像力で、自ら現実を引き寄せたように見えます。旦那さんは、あれで見初めた、そして探した。「世界の片隅」から彼女を見つけた。それに大して、すずが礼を言う。
「片隅」にいるのを見つけてくれてありがとうってのは、出会った瞬間を指しているのか、あのあと探し回ったことを言うのか……
飯田 僕は後者だと思いますね。というのも、偶然ないし強いられた状況がまずあって、でも、そのなかでいかに主体的に選択するか、引き受けるかをずっと描いている作品だから。
冒頭に関して言えば、想像なのか現実なのかわからない精神状態で生きていたってことじゃないのかなあ。「ぼんやりした子」の認識ではこうだったと。「海を跳ねるトビウオがうさぎに見える」のと同じレベルでの認識というか。
藤田 トビウオがうさぎに見えるのは想像力ですけど。籠で二人を連れ去ろうとした(とすずが思っている)怪人(?)は、すずの作った「物語」の中にまず出てくる。
しかし、大人になった二人が話している橋の後ろも歩いている。あのリアリティの水準の揺さぶり方は、奇妙で、本作の狙いを解釈する際に重要かと思います。「絵を書くこと」=「アニメを作ること」で、現実そのものを変えようとする、幸福な未来を引き寄せようとする意志を象徴する作品と読めるようになるのならば、この世界を単に諦めて受け入れる映画であるとする解釈とは異なってきます。
飯田 ありし日の姿や不在の人物は想像と資料、記録の中にしかない。みたいなことも言っていた(描かれていた)と思うし、そうすると回想と空想は本質的に区別がない……いや、そこまで強い主張をしている作品ではないですけども。
終盤に関しては、絵を描けなくなって空想する力をなくして「現実」に生きていたすずが、戦争が終わって再び空想できるようになったことの象徴、というのがきれいな解釈かなと思います。
すずの人格造型――
藤田「別世界」とか「こうもありえた人生」を想像することを抑制、ないし、あんまり考えないことが彼女を救っている、っていうのは、なかなか面白いメッセージ性を持っていますね、現代に対して。
「もし別の人と結婚していたら」、「もし広島に帰っていたら」、「もし反対側の手を繋いでいたら」…… それらを考えないわけではない。しかし、抑え込む。しかし、現実を上書きする想像力はある。不思議な人物の佇まいです。
飯田 意識的に「抑え込む」感じではないと思ったけども。すずは、ふわっとしているようで、地に足がついている。どっかに消えたり逃げたりしない。たいへんなのに。われわれは現代との対比で労働に関して「つらそう」と思うけど、それが当たり前の環境で育てば「そういうもの」と思うでしょう。
藤田 あんな重労働してニコニコしてるなんて、ありえないよって思っちゃったw
映画の肝となるキャラクターだし、彼女がああじゃなきゃ成立しないのは分かってても、なんかそこが気になった。腰曲がったりしないのかなとか、手があかぎれたりしないのかな、とか。「リアリティ」とか言うなら、ああいう生活していたら『楢山節考』のババアみたいな見た目になるはず、とかも思う。そういうところは観客はどう処理してるんだろう。
飯田 そのへんのやわらかさは、すずという人物造形の魅力というだけではなくて、こうの史代さんの漫画、片渕監督のアニメだからこその着地だなとも思います。ノベライズも読んでみたんだけど、文字で読むとふしぎと実写のキャラクターをイメージしちゃうんですよ。だからどうしても重たい。ああいう雰囲気、ああいうキャラクターデザインの漫画やアニメだからやわらかく受け止められるところがあるなあと。
こうの史代さんの原作漫画は表現とか間の取り方とかが独特なので(筆を使ったり、かるたみたいなコマ割りにしたり)、そもそも映像化が難しい。さらに言えば、こうの漫画は線に宿るユーモアがあって、それは容易に映像にできない部分です。
だけどちゃんと『この世界の片隅で』の映画になっていた。すずが描いた絵の世界と、すずが見ている現実が重なるような表現が原作からあって、違和感なく映像にするのは本当に大変だったと思うけど、見事。トビウオが海を跳ねる様子がうさぎに見えるシーンなんてスペクタクルになっていたし。晴美が亡くなった時限爆弾のシーンで、真っ黒な画面に花火みたいなものが描かれていって……という、『エヴァ』の終盤みたいな実験的な手法が使われているところも忘れがたいし。だけど兵器の描写は徹底してリアルだし。ふしぎなリアリティレベルの作品でした。
藤田 時限爆弾と、空襲と、先ほど飯田さんが仰っていた原爆その他の描き方はとても良かったですよ。空襲なのにカラフルだったりする、そういう色のときもあるんだな、っていう、説得力があった。
飯田 現実とは思えない、思いたくないときの感覚がよく出てましたね。
藤田 どうだろう。悲惨なことを引き起こすことなのに、美しい色をしているという「現実」の表現なんじゃないだろうか。
飯田 ああいや、時限爆弾のシーンのことね。
あとは、食べるものがないなかで道に生えてる草を採って工夫して料理するところとか、ああいうディティールもすごいよかった。監督自身が貧困というかギリギリの生活をしながら作ったというのがなんともではあるのですが。アニメ界の末端の生活の苦しさと重ねると……ね。
藤田 原爆も、遠くから体験すると、あんな盛り上がりに欠ける、アンチクライマックスな感じでさらっとしたものなんだな、っていうのも良かった。観客は日付で色々分かっているから、ハラハラさせつつも、ああいう風に流して描いちゃう。
貧困と戦争のディティールをこれだけ詳細に書くアニメが作られる時代の不穏さに、ちょっと怖くなったりしましたけどね。ぼくらは「戦争」のイメージをステレオタイプに思いすぎていて、実際にそれが近づいてきたり、既に起こっていても、普通に楽しく日常を過ごしているから「起こっている」と感じられないんじゃないか。作品が、そう突きつけてくるようにも感じました。