昭和の名選手が語る、
"闘将"江藤慎一(第4回)
前回を読む>>
1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手がいた(2008年没)。ファイトあふれるプレーで"闘将"と呼ばれ、日本プロ野球史上初のセ・パ両リーグで首位打者を獲得。
※ ※ ※ ※
江藤慎一と中日ドラゴンズで同僚だった権藤博
自称熊本太郎こと、江藤慎一のルーキーシーズンは、全試合出場で打率.281の打撃十傑6位、本塁打15本、84打点という好成績で幕を閉じた。例年ならば、文句のない新人王であったが、この年(昭和34年)は大洋ホエールズの桑田武が新人として歴代最高の31本塁打を放ったために無冠に終わった。
それでも初年度からレギュラーに定着してのベストテン入りは出色であり、鳴り物入りで入団した他の中日の新人たちに比べてテスト生あがりのノンプロ出身ということで、地味であった江藤の存在感がこれで不動のものとなった。
この年、繊細な板東英二は、西沢道夫の引退試合で見た杉浦忠(南海ホークス)の速球の威力と先輩や同僚たちの嫉妬によるいじめから、一時は鬱に苛まれたが、後半に持ち直し、4勝4敗の成績をあげた。
高校球界一の快速球投手と言われ、剛腕スカウト柴田崎雄が平岩治郎代表から、「あいつだけは何が何でも獲れ」と厳命されて、保護者に秘密裏に逢うために定光寺(愛知県瀬戸市)に日参して獲得した河村保彦は4勝7敗。
気の毒であったのは、立教大から、ポスト吉沢岳男を期待されて入った捕手の片岡宏雄であった。浪華商から六大学という野球エリートコースを進み、1年生から、板東を畏怖させた杉浦の球を受け続けた片岡は注目度が高く、本人も新人ながら移動バスのなかでロカビリーを歌い踊り、場を盛り上げる宴会部長として可愛がられていた。
しかし、周囲に向かって陽気に振る舞う人間ほど、その内面はデリケートである。吉沢の代わりに片岡がマスクを被った試合では、巧みなキャッチングが評価される一方、バッティングではノーヒットが続き、それが遠因か、イップスに陥ってしまう。
片岡は後にヤクルトでスカウトとして辣腕を振るい、1990年代のスワローズ黄金時代の礎を築く選手を多数、入団させているが、この時の苦労から新人選手に対する目利きや配慮が際立ったのではないかと思われる。
板東と片岡はキャッチボールの相手もつけてもらえずに、壁に向かって黙々と投げるという孤独な練習を課せられた。
江藤は12名の同期のなかでは圧倒的な出世頭となり、『巨人の星』の左門豊作よろしく1年目のオフに家族を熊本から名古屋に呼び寄せた。両親、そして3人の弟である。三男の省三は在籍していた熊本商業から中京商業への転校となった。
「とにかく家が貧乏でしたから。サラリーマンの親父の給料が月に1万円くらいで、それで食べ盛りの男4人を育てないといけない。近所に製糸工場の繭を乾燥する乾繭所(かんけんじょ)っちゅう所があったんですが、おふくろがそこで管理人として仕事をすることになり、うちはその工場の一画を住まいに貸してもらったんです。
その繭は年に2回、乾燥させるんだけど、あとは工場の敷地が全部空いてる。
名古屋に引っ越したのは、兄貴が新人のシーズン終わり、私が熊商の1年の12月で中京には翌年の1月から通いました。兄貴はプロでやれるなら、選手寮なんかにいるより、おふくろとおやじを呼んで暮らしたいという気持ちが強くあったんですね。おやじは田舎が好きで嫌がったんですけど。おふくろはもう早く行こうっちゅう感じでした。
熊商で1年から4番を打っていた省三も中京商業にはカルチャーショックがあったと言う。このチームは1年前(昭和34年)に平沼一夫(後に東京オリオンズ)、杉浦藤文(後に中京高校監督)、石黒和弘(後に東京オリオンズ)らの活躍によって春のセンバツを制している。決勝では高木守道を擁する県立岐阜商業を下しており、深谷弘次監督も当時「歴代最強」と明言していた。
「私の熊商時代は、夏の大会の決勝で末次(利光)さんのいた鎮西に負けて甲子園には行けなかったんですけど、県の代表にもなっていっぱしの選手になっていた気持ちでおったんですよ。それが、兄貴が勧めるのが中京一辺倒で、転校したら、春のセンバツ優勝校じゃないですか。グラウンドに行ったら部員が200人ぐらい固まっていてね。
しかし、省三も地力を発揮する。3年生となった1961年(昭和36年)には主将となり、同期の山中巽(やまなか・たつみ)、1年下の木俣達彦とともに主力を担って春夏の甲子園に続けて出場、慶応大に進学していく。プロ(巨人、中日)を経て、やがては母校慶応の監督に就くという充実した野球人生を送るのだが、その幼少期より兄は父代わりと言えた。
父の哲美がシンガポールに出征していた大戦中、母の判断で江藤家が空襲を逃れて疎開をする際、当時7歳の江藤が幼い省三を背負い、右手に持てるだけの荷物を持ってあとに続いた。その姿を見て母親は「メダマ金時(金太郎)ごたぁる」と言った。幼いながらに頼もしさを見てとったのであろう。
「私が現在あるのはもうすべて兄貴のおかげですから。『自分は大学に行けなかったから、弟はみんな俺が進学させてやる。親父は何もしなくていいよ』って、父親にも言ってくれてね。私も頭が上がりませんでした。巨人に入団した時に中日戦になると、兄貴がベンチに『おい、元気か』と訪ねて来るのですが、直立不動で『はい。元気にやっています』とあいさつしました。それを見た柴田(勲)なんかが、『何で兄弟に敬語を使っているんです?』とか言うんですが、私にとっては普通のことでした」
大黒柱となった江藤の生活は一変した。開幕前はオープン戦で同室となった同期の外野手・横山昌弘に名古屋の繁華街、栄に連れて行かれても琥珀色の液体に口をつけられなかった。
「どうした? ビールは嫌いか。俺のおごりだ。飲め」「いや、これを飲んだことがないんです」
日鉄二瀬時代に嗜んだのは、焼酎かドブロクのみ。初めて口にしたビールの味はこれ以上なく美味で、たちまち1ダースを空けた。プロは結果を出せば、すぐにカネになる。本塁打の賞金が5000円でこれだけでも飲み代は賄えた。さらに人気選手には、酒食をご馳走するタニマチもつく。名古屋ローカルはまたそれが盛んな土地であった。
江藤は酒の味を覚えた。2年目(昭和35年)の成績は打率.252、本塁打は14本。頭打ちと言われる成績であった。ノンプロ時代は日中に仕事をしてから、職場に気を遣って練習に向かい、ヘトヘトになるまでボールを追い、寮に帰れば倒れるように眠るだけであった。しかし、プロはカネも時間もたっぷりとある。ケタ違いの収入がある上に盛り場では、下にも置かない扱いを受ける。かつて才能ある選手たちが、どれだけこの誘惑に堕ちていったことか。
ある夜、江藤が帰宅すると、母が縫物をしていた。すでに時計の針は午前3時を回っている。背を向けたまま針を動かし続ける母は言った。「慎ちゃん、あなたの腕でかせいだお金ですもの、あなたの勝手に使っていいのよ。でも身体だけは大事にしてね。お母さん達は、松橋の方へ帰って、もう一度はじめからやり直しますから」(『闘将 火と燃えて』江藤慎一・鷹書房刊)
急ぎの縫い物など、あるはずもなく、母は諫言(かんげん)のために起きていたのは明白だった。頭から冷水をかけられた思いだった。江藤はこれ以降、翌日に残るような深酒を断った。
入団3年目(昭和36年)は打率.267、本塁打20本と持ち直して初のベストナインを受賞する。
中日はこの年に大きな変貌を遂げていた。前シーズンより中日二軍監督に就任していた日鉄二瀬時代の恩師・濃人渉(のうにん・わたる)が監督に昇格していたのである。加えて、ブリヂストンタイヤから入団した新人投手の権藤博が超人的な活躍を見せてチームも2位に食い込んだ。
権藤は429.1イニングを投げきり、35勝、32完投、12完封という圧倒的な数字を残した。「権藤、権藤、雨、権藤」の惹句(じゃっく)はこの時に生まれた。入団した権藤はノンプロ時代からよく知る江藤の打撃の変化に驚いていた。
「九州で2年間、ブリヂストン鳥栖と日鉄二瀬で戦っていましたから、その時以来のつき合いですよ。正直、私は、彼はプロでは通用しないと思っていたんです。二瀬の野手は練習でグラウンドの場外に打たないとプロには入れないと言われていたんです。寺田(陽介、南海に入団)さんなんかは、ガンガン振り回してその際たるもんでした。江藤さんも大上段に構えて遠くに飛ばしはしていましたが、穴が大きかった。キャッチャーで4番を打っていて、当たれば大きいというタイプ。しかし、私がカーブを投げたらほとんど打たれなかった」
当時のエネルギー供給源のトップが石炭という時代、二瀬炭鉱の野球チームは豪胆を以て尊ぶ気風があり、都市対抗を応援する社員や地元の炭鉱夫たちもそれを支持していた。練習で場外に打てないとプロには入れない、というひとつの伝説の下、江藤もまた次のステージに行くために振り回していた。その穴をブリヂストンのクレバーなエースは看破していた。
「ところが、チームメイトになって見たら構えがガラッと変わっていた。バットを心持ち寝かすようになった。それがすごい。オープン戦で見た時にシュアになっていて、プロのコーチはさすがだと思ったもんです。『大したもんですね。江藤さん、誰が教えてくれたんです?』『いや、博。誰かに教わったわけじゃないんや。俺はプロに入って自分でこれじゃあかんと思って変えたんや』。
彼のすごみはバットマンとしてのその切り替えのよさ。自分ですべて考えてプロに適応していく生き様がすごい。それでセ・パ両リーグの首位打者を獲ったんです。それは王(貞治)さんにも言えていて、私は、1年目は王さんにほとんど打たれなかったのですが、2年目に一本足打法になってから打たれた。王さんもまた変化を恐れない人でしたからあれだけの成績を残したんでしょう。よいバットマンに共通して言えるのは、生き残るために自分で突き詰めて考えて変化を恐れない勇気ですね」
江藤の右投手の外角スライダー打ちの技術についてはこう言った。「むしろインコースが打てなかった。だけど、あれだけの迫力では投手は懐には投げられない。そこでインコースは捨てて踏み込む。外角へのスライダーは彼にとってはカモですよ」
権藤は2年目も362.1回を投げて30勝をあげたが、以降は肩、肘を痛めて10勝、6勝と先細りになり、4年で投手を断念し、野手への転向を余儀なくされている。
紛れもなく酷使の影響だが、社会人時代に日鉄二瀬の補強選手として都市対抗に出場して以来、中日入団に際しても権藤と濃人との関係は深く、権藤は太く短く終わった投手生活について悔恨がましいことを一切、口にしていない。
「毎日投げろ、と言われても何とも思わなかったですね。プロで一旗あげてやろうと九州の田舎もんが都会に出て来たわけで、元々内野手だから、肩もすぐできた。仕事があれば投げるだけですよ」
それでいて経験主義に陥らず、投手コーチになってからの権藤は、無理な連投を教え子たちには絶対に強いなかった。「それは自分で肩の痛みを知っていたからです。僕の指導者としての成功は顔をゆがめながらも投げていた頃の痛みを覚えているからですよ」
選手の人生を考え、俺の若い頃は......という消費をしなかったことで多くの投手に慕われた権藤は、監督としても横浜ベイスターズを日本一に導いている。
江藤の置かれた当時の環境を拝察するためにこの権藤が入団した年の中日のチーム状況をしばし、記述したい。昭和36年シーズンは江藤の再起、連投上等で投げまくった権藤の他にも、地道な努力が開花した板東が12勝、河村も13勝をあげた。勝率の差で2位に甘んじたが、勝ち星は優勝した巨人よりひとつ上回っており、結果だけ見れば、濃人は評価されて然るべき監督であった。
しかし、チーム内は不穏な空気にまみれていた。濃人と生え抜きの選手との対立である。チーム改革に乗り出した濃人は、5位に転落していた前年のオフにも大矢根博臣、伊奈努のローテーション投手を放出しており、聖域化されていたレギュラー、地元出身選手にも容赦なくメスを入れた。
叱咤する言葉も厳しく、4番の森徹にも遠慮会釈がなかった。長嶋茂雄の同期で早稲田大から入団していた森は2年前に本塁打と打点の二冠を獲得しており、スターの地位を確立していた。森は板東同様に旧満州出身で、当地で手広く商売をしていた母親が力士時代の力道山を可愛がり、新京(現・長春)などに巡業に来た際には、何くれと面倒をみていたので、このプロレス界のスーパースターと子どもの頃から親交が深かった。
契約時には立ち合い人を務め、中日球場の練習にも顔を出す後見人が力道山ということで森は、新人時代から一目も二目も置かれる存在であった。それでも濃人は粗の多い森の打撃にダメを出した。23歳でホームランキングを取ったプライドは傷つけられ、反発する。
星野仙一が中日や阪神で「血の入れ替え」を行なったように、従来監督は、球団の歴史を分断しても自らが取ってきた手駒で勝負をかけたがるものであり、また12球団一、選手を甘やかすと言われていた東海地方唯一のチームに刺激を与える必要があったとは言え、あまりに感情的にもつれすぎた。濃人と森、井上登、吉沢、横山、広島衛、酒井敏明、石川緑ら、主力との対立は決定的となった。
結局、森は大洋に、吉沢と甲子園優勝投手の児玉(空谷)泰は近鉄に、石川は阪神に金銭トレードで出されてしまった。酒井と広島は退団というかたちをとった。
森はこの後、大洋、東京オリオンズと移籍を繰り返すが、4年しか在籍しなかった中日への愛情は強く、引退後に監督兼選手として参加したグローバルリーグ(大リーグに対抗して創設されたもので米国、日本、ドミニカ、ベネズエラ、プエルトリコの5か国で国際リーグ戦を行なうという構想の組織)では、所属の日本チームの名前を東京ドラゴンズと命名している。その愛着からも放逐された無念さは伝わってくる。
一方で濃人が熊本出身の江藤や久留米出身の権藤を重用したことで、地元記者やファンからはいわゆる濃人によって作られた「九州ドラゴンズ」と揶揄された。
先輩選手が放出され続けるなかで、3年目の江藤はこの嵐の下で孤立するより他なかった。濃人の改革旋風が吹き荒れた昭和37年のシーズン、中日は5月26日から6月6日にかけて10連敗し、最下位に転落した。
特に捕手は吉沢と酒井を出してしまったことで、人材が枯渇し、杉下監督時代に失格の烙印を押された江藤を捕手に戻すという有り様だった。事態を重く見た高田一夫代表は米国に飛び、ローレンス・ドビー、ドナルド・ニューカムという元メジャーリーガー選手を入団させた。日本球界には、かつて1953年にはレオ・カイリー(ボストン・レッドソックス→毎日オリオンズ)、フィル・ペイン(ボストン・ブレーブス→西鉄ライオンズ)のふたりの大リーガーがいたが、彼らは朝鮮戦争下に日本の朝霞基地などに兵役で来た進駐軍兵士であり、軍の公務に就きながら、いわばパートタイマーとして契約したにすぎなかった。
他にはジョー・スタンカが1960年にシカゴ・ホワイトソックスから南海に入団していたが、シカゴでは2試合しか投げておらず、実質は3Aの選手であった。その意味では、MLBで2度の本塁打王となったドビー、149勝を上げたニューカム(日本では外野手登録)は日本球界に初めてやって来たメジャーリーガーと言えた。シーズン途中ながら、ふたりの加入は大きな刺激となり、7月以降は勝ち越しが続いた。
柴田崎雄によれば、濃人が自身にとっても初めてとなるメジャーリーガーの起用を大過なく務めることができたのは、かつて米国との二重国籍であったからであり、その合理性からだと書き残している。
濃人が二重国籍であったのは、両親がハワイのカウアイ島に移住していたことから、出生届け出によって米国籍を自然と取得していたことによるものであり、広島で育った濃人自身は広陵中学(現在広陵高校)卒業後に数か月、ハワイで生活したことが唯一の米国体験でであった。しかし、1941年の日米開戦を控え、どちらかの国籍選択を迫られた際は少なからず「二つの祖国」を意識したであろう。
濃人には米国人選手へのリスペクトこそあれ、偏見なく接していたのではないかと思われる。監督とのコミュニケーションが円滑に取れたドビーとニューカムはアーチをかける度に並外れたメジャーのパワーを示して活躍した。
しかし、これもあくまでもそれはカンフル剤的な効果でしかなく、愛すべき選手の多くを失ったことで、チーム内も外もすでに濃人のやり方には、不満が渦巻いていた。「名古屋は難しい」とは40年後にこのチームの指揮を執った秋田出身の山田久志の言葉でもある。
濃人のチームの結果が出てもOBや評論家、地元のファンはこれを支持せず、観客動員数も落ちていった。恩師と慕った江藤もまた板挟みとなり、「ボクだって、オヤジさん(濃人)のやり方を疑問に思うよ」(『ドラ番三〇年』森芳博・中日新聞本社刊)と漏らすほどであった。
それでも孤軍奮闘を続け、最終的には打率.288 、本塁打23本と野手のなかでは最高の成績を収めた。チームも大リーガーコンビの活躍で、借金10から持ち直し70勝60敗で3位に滑り込んだ。2年連続のAクラスであった。これで指揮官の続投は既定路線とも言われていた。しかし、12月10日に高田代表は突然、濃人の更迭を発表した。
この監督人事を権藤は「確かに濃人さんはケガをしていてもすぐに痛い痒いを言わない九州の選手が好きだったでしょう。しかし、それにしても急な解任は名古屋らしい風土の結果です。私に言わせれば、落合(博満元監督)と同じですよ。落合のチームだってあれだけ強かったのに野球が面白くないとか、客が入らないとか言われて叩かれる。落合が解任された時にああ、あのときに似ていると思ったものです」
江藤は前年のオフにタカラジェンヌの瀬戸みちると結婚していた。無骨な男が、デートで映画『ベン・ハー』に誘い、瀬戸の最後の舞台となる『華麗なる千拍子』も見に行った。知り合って3年越しで成就させた結婚であったが、その仲人との別れでもあった。
中日は濃人を解任し、地元出身でチームのOBである杉浦清を15年ぶりにパイロットに据えた。これもまた落合から高木守道へのバトンパスの相似形と言えなくもない。
江藤はリーディングヒッターへの道を歩んで行く。
(つづく)



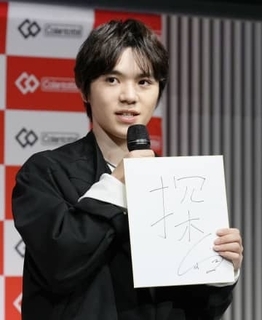





























![Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 “GIFT” at Tokyo Dome [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41lC7CBti1L._SL500_.jpg)
![プロローグ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/31gi5M5UkOL._SL500_.jpg)