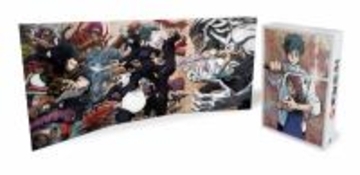第3週「一生笑わしたる」第16回 10月19日(木)放送より。 (16話レビュー)
脚本:吉田智子 演出: 本木一博
連続朝ドラレビュー 「わろてんか」はこんな話
京都の薬種問屋の長女・てん(葵わかな)は、子供の頃、地元のくすり祭りで、芸人・藤吉(松坂桃李)と出会い、心惹かれる。藤吉も、自分の芸にはじめて笑ってくれたてんのことを忘れられず、その後、8年もの間、
手紙を出し続ける。
8年後、偶然、くすり祭りで、ふたりは再会。さらに強く惹かれ合うが、てんには縁談が持ち上がっていて・・・。
実際の“くすり祭り”が11月2日に開催
てんと藤吉の最初の出会いも再会の場も同じくすり祭り。
運命の場所であり、祭りである、くすり神社とくすり祭りが、京都の実際のものとは大きくちがうことは、すでにSNSで情報通の方々が書いている。
「京都」「くすり神社」「くすり祭り」などのワードで検索すると、京都二条の「薬祖神祠」と「くすり祭り」に関する記事もでてくるが、実際、この目で見てみたかったので京都二条通りに向かった。
京都駅から烏丸線に乗り烏丸御池駅で降りると歩いて10分くらいのところにあるが、あえて、朝ドラ「あさが来た」(16年)のモデルになった広岡浅子の生家の一部だったとされている〈ルビノ京都〉という宿泊施設から歩いて行ってみた。
堀川通を(南へ)下がって丸太町通りを東へ入り、両替通りを下がって二条通りを東に入る。あらこんなところにこんなお店が・・・などと脇目もふらず一心不乱に歩いてだいたい15分くらい。建物と建物の間に鳥居が収まった「薬祖神祠」があった。


神社ではなく、無人の祠である。
中はガラス戸で閉ざされていて、中にはもうひとつ鳥居があるがその奥は神秘。手前には、ドラマ1話にもちらっと映ったヒポクラテスの頭像も飾ってあった。
向かって右となりの建物・二条薬業会館に「くすり祭り」が11月2日開催されると書いたちらしが貼ってあり、詳細を知りたかったが、会館は留守。
京都市役所、中京区役所に訪ねてもわからず、ネットでみつけた電話番号にかけてもFAXになってしまう。
左隣りのくすり屋・山村寿芳堂(寿は旧字)さんに聞いてみたが、山村さんが管理しているわけではないという。
聞けば、「京のくすり祭り協議会」という会が管理していて、去年までは共栄薬品さんが、今年から日本新薬さんが会長をつとめていることがわかった。
昔はかなりたくさんの薬問屋さんが参加していたのがいまでは30社ほどに減ってしまったとはいえ、薬祖神祠の歴史を引き継いでいくべく、残った方々で神社をお守りしている。
1年に1度、ガラス戸を開いて、行われるお祭りも、以前は、二条通沿いに縁日などもあったが、いまでは、神事のみ。宮司さんによるお祓いと、お神楽舞があって、一般人も見ることは可能だ。
ほかには、お祭りのときだけ、笹についた寅のお守り(無病息災)が販売される。
元は中国から伝わった、寅の頭の骨が薬になったという話から、寅は薬祖神祠の神様・神農さまのシンボルで、各地にあるくすり神社でも寅が飾られている。実際、昔、日本にも寅の骨を配合した薬があったとか。
11月2日、くすり祭りをのぞいてみたくなった。

なぜ、ヒロインは京都生まれに設定されたのか
「わろてんか」のくすり神社とまつりを描くにあたって、NHK大阪のスタッフも何度も足を運んだらしいが、実際、放送されたものを見た地元の方々の中には、まったく違っていて驚いたと言っている方もいるという。確かに、まったく違うから無理はない。
京都の二条通でロケするのも、セットを作りこむのも難しいだろうし、昔を描くためにはいろいろ大変だと思う。「わろてんか」の場合は、滋賀県の油日神社でロケして、ドラマのはじまりにあたって広がりのある風景を描く工夫をしてみたのだろう。
実際の“くすり祭り”が11月2日に開催
そんな無理をしながらわざわざ京都のくすり問屋をヒロインの生家にしたわけはなぜなのか。
モチーフにしている吉本せいは、兵庫の米問屋の娘で、ドラマでは藤吉の家が米問屋になっている。
「わろてんか」の予習に最適な数々の参考文献のひとつ、噺家・桂春団治に関する書物を読むと、(例えば、富士正晴『桂春団治』)想像が膨らむ。
春団治は、『わろてんか』のヒロインのモチーフになっている吉本せいのつくった吉本興業に所属する売れっ子落語家。長くなるので彼についてはいまここでは詳しく書かないが、春団治の妻が京都の生まれ。二番目の妻が薬問屋の後家さん。そして、桂春団治の本名は「藤吉」。
どうやら、「わろてんか」は、吉本せいのほかに桂春団治のエピソードなども大小とり混ぜて、オリジナルストーリーをつくっているようだ。このふたりだけでなく、ほかにもモチーフになっている有名人物がいるかもしれないので、元ネタ探しが楽しめそう。
でもこうなると、「わろてんか」には、桂春団治的な人物は出てこないのか。
(木俣冬)