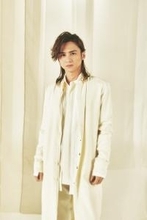いずれの番組とも春風亭昇太が出演しているが、それぞれキャラクターがまったく違う。
それが先週放送の「直虎」で、義元が上洛の途上、とうとう桶狭間で織田信長に殺された。はたして昇太は、義元の最期をどう演じるのか。当日は期待しながらBSプレミアムにチャンネルを変えたのだが、まさか、昇太の出番がないまま桶狭間が終わってしまうとは予想もつかなかった。義元の死は、戦いが終わったあと、ひとつ残された扇によって暗示されるのみ。ただ、それがかえって突然の死の衝撃を強く印象づけていたようにも思う。

信長の出てこない桶狭間
「直虎」の桶狭間の回では、信長が登場しなかった。そこで思い出したのが、2007年の大河ドラマ「風林火山」である。第45回「謀略!桶狭間」では、戦いを前に信長についてさまざまな情報が、主人公で武田家に仕えた軍師・山本勘介(内野聖陽)のもとに集まってくる。だが肝心の信長は、「敦盛」を謡いながら舞うシルエットのみの登場。それでいて、正体不明なところが、かえって不気味さを際立たせていた。
「風林火山」では義元を谷原章介が演じた。大河にかぎらず多くの時代劇で義元というと、馬に乗れなかったとの話からか、でっぷりと太り、公家気取りで武士らしさなどみじんもない姿で描かれがちだ。
その劇中では、勘介が義元に、信長についての情報を与え、助言する。だが、それがかえって義元を翻弄することになるという展開が見ものだった。
1988年の大河「武田信玄」でも、山本勘介(西田敏行)が義元の命運を左右する役回りを担った。同作で義元に扮したのは中村勘九郎(のちの18代目中村勘三郎)である。信長(石橋凌)軍に急襲され、血まみれで「都へ……都へ……」と口にしながら死んでいく義元の姿は、いかにも無念さにあふれ、強い印象を残した。このとき勘九郎は32歳。義元の実年齢どころか、彼の長男で現在の勘九郎(35歳)よりも若かったことになる。
桶狭間が夫婦の出会いのきっかけに
歴代の大河ドラマのうち、映像がNHKに現存するもので桶狭間の戦いが出てくる作品は11本を数える(当該シーンの映像は現存しないが、おそらく出てくると思われる1969年の「天と地と」も入れれば12本)。
最初に登場するのは「太閤記」(1965年)で、桶狭間の回こそVTRは残っていないものの、唯一現存する第41回「本能寺」では、信長(高橋幸治)が死ぬ間際、走馬灯のように自らの人生を回想するなかで、義元殺害のカットが使われている。ちなみに、このとき義元を演じたのは、司会や文筆業でも活躍した元祖マルチタレントの三國一朗だった。
義元のルックスにも作品ごとに結構バリエーションがあり、前出の勘九郎は白塗りにしないまでも公家風の引き眉に加えお歯黒。「徳川家康」(1983年)の成田三樹夫は薄っすら白塗りにお歯黒。これに対し先の谷原章介や、「功名が辻」(2006年)の江守徹のように、とくに化粧をほどこしていないケースは少数派といえる。
「功名が辻」、それから「おんな太閤記」(1981年)では、桶狭間の戦いが初回に登場する。いずれもヒロインが将来の夫と出会うという点でもこの2作は共通する。
「功名が辻」では、少女時代のヒロイン千代(永井杏/仲間由紀恵)が、偶然にものちの夫・山内一豊(上川隆也)と出会う。一豊はこのとき、仕えていた岩倉織田家を信長(舘ひろし)に滅ぼされ、同家の家老だった父を失ってまだ間もなかった。そのため信長を仇と憎みつつも、行きがかり上、桶狭間の戦いに参戦、信長方につくことになる。
一方、「おんな太閤記」の冒頭は、信長(藤岡弘)が清洲城を出陣するシーンから始まり、あっけなく義元(新みのる)との勝負が決する。ヒロインのねね(佐久間良子)は、凱旋する信長を迎えた際、将来の伴侶となる藤吉郎(のちの豊臣秀吉。
似たようなシーンは「秀吉」(1996年)もあり、このときは桶狭間からの凱旋の際に、竹中直人演じる日吉(のちの豊臣秀吉)がおね(沢口靖子)にプロポーズする。なお、同作では義元を米倉斉加年が演じた。白塗りの義元と、泥にまみれ真っ黒になりながら戦場を駆け回る秀吉はいかにも対照的だった。
「桶狭間は時の狭間」
「功名が辻」の山内一豊と同じく、「利家とまつ 加賀百万石物語」(2002年)の前田利家(唐沢寿明)もまた、信長とのあいだにわだかまりを抱えながら桶狭間に出陣する。その少し前に利家は信長(反町隆史)の怒りを買い、勘当中の身にあった。戦場では敵の首を取るも、義元(佐々木睦)以外の首はいらないと、けっきょく武功は認められずじまい。
同じ回(第4回)では、出陣を決めた利家に、戦場近くで父・利昌(菅原文太)が勝軍地蔵を渡すというシーンがあった。息子を見送ったのち、戦況を眺めながら、時代の変化を悟った利昌は、その日のうちに「桶狭間は時の狭間」との言葉を遺して逝く。後日、利昌の死が思わぬ形で、利家と信長が和解するきっかけを与えた。
なお、「功名が辻」では、義元が陣取った場所として「桶狭間山」という地名が登場した。これは『信長(しんちょう)公記』の記述にしたがったものだろう。これに対し、同じく司馬遼太郎原作の「国盗り物語」(1973年)では、「田楽狭間」との呼称が採用されていた。
信長が死を覚悟して向かった桶狭間
ところで、多くの時代劇では、信長は義元に勝つと絶対の自信を抱きながら出陣したものとして描かれがちだ。しかし実際はどうだったのか。「信長 KING OF ZIPANGU」(1992年)では、緒形直人扮する信長が、多勢の今川方に対し自軍は無勢と、死を覚悟して桶狭間に向かう。むしろこちらのほうが現実に近かったのかもしれない。
同作はさすが信長が主人公とあって、桶狭間の戦いは第13回と第14回の前後編にわたって描かれた。信長とは対照的に、義元は当初は自信満々だったのが、最後の最後で輿に乗せられ、さんざん逃げ回ったあげく、とどめを刺される。
このときの合戦シーンは、いつにも増して大がかりな野外ロケだった。ただ、野外ロケは天候に左右されやすい。「信長」の本放送時、高校生だった私は、「大雨が降ってるのに、あきらかに晴れ間が出てるじゃん!」とついツッコミを入れてしまったものである。もちろん、テレビドラマはスケジュール的にも縛りが厳しいだろうから、そこを責めるのは酷だとは思う。
考えてみれば、歴代の大河で桶狭間をとりあげた作品のうち、私の印象に残っているのは「風林火山」や「武田信玄」など、どちらかといえばスタジオで収録されたもののほうが多い。それというのも、映像の不自然さを気にすることなく見られるからというのも案外大きいのかもしれない。
(近藤正高)