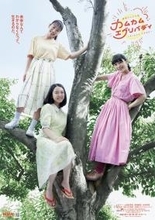第11週「あかね荘へようこそ!」第62回 6月13日(火)放送より。
脚本:岡田惠和 演出:福岡利武

62話はこんな話
1966年1月4日、今日から仕事はじめ。みね子(有村架純)は髪型を変えて初仕事に臨む。
忘れない、茨城推し
ポニーテールにしたみね子。うなじのラインがいい感じ。
制服着た姿も、ウエストがきゅっとしまって、大人感が出ている。
制服に関しては、先輩の高子(佐藤仁美)と比較して、「こういうデザインだったんだねえ」と繰り返し強調するところが愉快。意外とシビアな話だと思うが、それを笑って済ませられることが、すずふり亭の風通しの良さだ。
あかね荘の大家・富(白石加代子)の「若い頃は夜輝く女だったもんで」という名言だとか、みね子の前に住んでいたのは、すずふり亭の見習いコック前田秀俊(磯村勇斗)だったとか、みね子の笑いのツボだとか、押さえておきたい要素がちょいちょい入ってくるが、62話のポイントはなんといっても“茨城”だろう。
まず、すずふり亭で使用しているお米が宮城県産だったことに、「ちょっと悔しかったです」と語るみね子。
「ひよっこ」、じつは、お米愛に貫かれていたのだと気づいた。確かに、稲刈りを一話まるまる使って描いたり(6話)、三男(泉澤祐希)が米屋で働いていたり、“米”のことを忘れないようになっている。
さらに「ねぎは茨城産です。なんかうれしいです」と、ひたすら茨城(いばらきの“き”を強調した発音)推しだった。それはとても大事なことだと思う。
お仕事をどう描くか
正月3が日過ぎたらすぐお仕事。
厨房にやって来る人たちは、軽く、お正月の挨拶をする程度で、いつものあまり変わらない自然な態度。
みんな、いつもの自分の仕事をしている。
まずは、下ごしらえ。
広場に出て作業していると、中華料理店や和菓子屋の人たちも出てきて、仕事の準備をはじめる。
この広場、いろんな人たちが時に集まり、すぐまた自分たちの空間に戻っていく、ベタに言えば、人間交差点的な場所だろう。
ちょっとした仕事のはなし。道具の調整や、できの悪い小豆もゴミじゃなくうまく炊けばいいあんこになるとか、そういうやりとり見ながら、みね子はお父さんに向けてつぶやく。
「お父さん、みんなの働く姿はすてきです」
「何だかこの裏の広場はまるで工場のようで 準備がどんどん進んでいきます。そしてみね子はこういう時間が大好きです」
「(前略)食べ物やさんが並ぶ商店街の裏にはこんな工場が日本中にあるんだなと思ったらなんだか楽しくなります」
向島電機の工場も、新しい職場も、同じ志ある者たちの場所なのだ。
工場はものを作る場所。英語で言うとファクトリーで、ちょうど同時代の64年に、ニューヨークでは、アンディ・ウォーホルがファクトリーという拠点をつくり、制作活動を行い、そこにはたくさんの才能あるアーティストが集っていた。この広場に集まっている人たちは、芸術家ではなく、労働者だが、ものをつくる根本は同じなんじゃないかと思う。
(木俣冬/「みんなの朝ドラ」発売中)