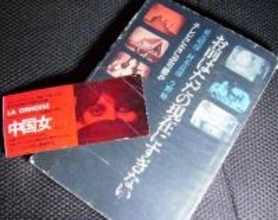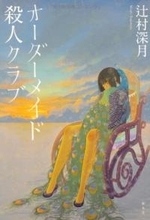「漢」と書いて「おとこ」と読んだのは『魁!! 男塾』。
そして2013年、「監督」と書いて「おとこ」と読む本が登場した。
『高校野球 神奈川を戦う監督(おとこ)たち』
甲子園を目指して全国各地で戦いが始まった高校野球地区予選において、最激戦区として注目を集める神奈川県の野球部監督・コーチ9人を追いかけたスポーツ・ノンフィクションだ。
桐光学園の松井裕樹投手の活躍で、例年以上に盛り上がりを見せる神奈川県高校野球。スポーツ紙だけでなく一般紙やテレビ番組でも特集が組まれ、春季神奈川大会での松井裕樹出場試合では保土ヶ谷球場が満員札止めになったほど。
だが、一人のスター選手だけの力で勝ち上がれるほど神奈川の戦いは甘くはない。「神奈川を制する者は全国を制する」という格言があるのは、毎年神奈川のレベルが高く、その熱戦を見守る熱心なファンを生んできたからだ。
本書によれば、年によって多少の違いはあるものの、「夏の神奈川県大会の有料入場者数は約20万人。入場料は一般500円のため、単純計算で1億円を超えるビックイベントとなる」という。目の肥えたファンの厳しい視線があるからこそ、競技レベルもまた高まっていく。
一方でこの「観客の数」が、球児たちにとっての新たな敵にもなるという。
「表現は悪いですが、神奈川の敵はスタンド。県立高校が勝てないのは、『スタンドに負けるから』といってもいいくらいです。
だからこそ、前評判の高いチームが敗れるといったドラマが生まれるのであろうし、そんな状況下で勝ち上がることが「神奈川を制する者は全国を制する」ことにもつながってくるのだろう。
しかし、高校球児が甲子園を目指して戦えるのはわずか2年半だけ。球児たちが入れ替わっていく中で、それでも神奈川が強豪県であり続けるのは、ひとえに「監督」の影響力が大きいということを本書は改めて示してくれる。
この中には、思わず「漢」とも書きたくなるような熱い監督が次から次に登場する。
「一生懸命やったやつしか、ラッキーボーイになれない。宝くじに当たる確率よりも低いからな」(桐光学園・野呂雅之監督)
「野球の文化をいかに広めていくか。少子化で野球人気も下がってきた中で、高校野球の指導者が持つ大事な役割だと思っています」(慶応義塾・上田誠監督)
「闘争心、折れない心、汚名を返上するような馬力。この心が育っているのは東海大相模だけだと思っています」(日大藤沢・山本秀明監督)
「環境は人が作る。その環境が人を作る」(県相模原・佐相眞澄監督)
「県立でも神奈川を勝つことができる」(川崎北・西野幸雄監督)
そして、「強敵」として目の前に立ちはだかる監督同士の交流が深いのも、神奈川野球の特徴であるという。監督同士が切磋琢磨し、ときにはアドバイスを送り合うことでさらにレベルが向上していく。
それが成り立つのも、横浜高校で70・80・90・00年代の各年代で全国制覇を成し遂げて来た渡辺元智監督&小倉清一郎コーチの存在があるからこそだ。
「横浜と同じ野球をしていては絶対に横浜には勝てないということです」(東海大相模・門馬敬治監督)
「横浜が強いことで神奈川全体のレベルが上がっていくと思っています」(慶応義塾・上田誠監督)
「横浜と勝ったり負けたりの中で、常に優勝争いに絡んでいくことが、次の甲子園につながると思っています」(横浜隼人・水谷哲也監督)
「横浜が強くなければ面白くない」(日大藤沢・山本秀明監督)
そんな追われる立場にある横浜の渡辺元智監督も、かつては東海大相模と原貢監督を越えるべき壁と定め、「打倒・原貢」を宣言することで今の地位を築いてきた過去がある。そして今は、原貢の教えを受けた東海大相模の門馬監督が、「打倒・横浜!」に執念を燃やす。数珠つなぎのように連綿と続いていくライバル関係が、さらに神奈川の野球のレベルを押し上げていく。
松井裕樹一人に注目するだけではもったいない、神奈川県予選の熱い舞台裏が本書『高校野球 神奈川を戦う監督たち』には詰まっている。高校野球観戦のお供としてもぜひオススメしたい。
(オグマナオト)