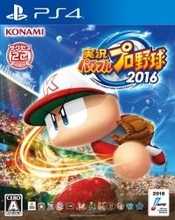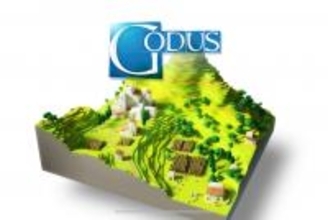本パネルは秋葉原で開催された「東京インディーゲームフェス2015」で5月7日に実施されたもの。パネリストは「牧場物語」シリーズのプロデューサーをつとめ、現在はトイボックスの和田康宏。「チュウリップ」など個性的な作風のゲームで知られ、新作「ミリオンオニオンホテル」を開発中というOnion Gamesの木村祥朗。ボストン出身の中国系アメリカ人で東京在住、東京インディミートアップも主催するDot Warrior Gamesのアルビン・フー。そしてPopCap Gamesで「プランツVSゾンビ」などに携わり、現在はFriend & Foeのマット・スミスの4名です。
大前提として今、前述のようにチェックボックス一つで、世界中にゲームを配信できる時代になっています。一方でライバルの数は無限大で、売り上げを増やすには世界に向けて配信することが半ば常識。そのための方法論には「ローカライズなどに相応の費用をかける」「ローカライズ不要で遊べるカジュアルなゲームを作る」があり、少人数・小資本のインディゲーム開発者なら後者を選ぶのがセオリー。しかし、それってホントに自分が作りたいゲームなのか・・・そんなジレンマがあると思ってもらえれば良いでしょう。
開口一番、強烈なくさびを打ち込んだのが木村です。
それでもテキストを追加することにしたのは、このままでは自分の味が出せないと感じたから。それだと、わざわざインディゲームで作っている理由がない。作りたいゲームに相応の理由があってテキストを入れないのは良いけど、世界で売りたいからテキストを入れないというのは本末転倒だというのです。「自分は日本人で、日本で作っていて、まずは日本人に遊んで欲しい。その視点を年末に取り戻した。世界で売りたいから言葉をなくすとか、全部英語にするとか、最近は好きじゃなくなった。
理由の一つに、木村は海外のインディゲーム向けイベントに参加した経験をあげました。そこでは、ちゃんと自分らしいゲームを作っていれば、ユーザーやメディアも注目してくれる。しかし、他と埋もれるようなゲームを作っていたら無視される。イベントを回っていろんな人に会ううちに、もっと自分の本性をゲームを通して表現していかなければいけない。そんなふうに思うようになったというのです。
もっとも、宣伝やSNSでの拡散などを否定しているわけではないとのこと。実際に「イベントに出ることが宣伝にもなるし、自分の学びにもなる」といいます。その上で「引きこもって黙々とゲームを作って、たまにイベントに出て、また引きこもって・・・を繰り返せば、何か良い物ができる。そうすると注目されるし、パブリッシャもつく」と説明しました。おもしろいゲームを作っても、売れないかもしれない。それをどうやって広げようかという議論もわかる。
こうした議論を引き取ったのが和田です。結局は自分がおもしろいと思うゲームを作るしかない。アメリカっぽいゲームを作っても、所詮は猿まねでしかなくて、ユーザーの心に届かない。日本人だけど、こういう物が良いという表現を、自信を持って進めるしかないと語りました。その上で「自分にとっておもしろいとは何か、本当にそのおもしろさが実現できるのか、それを突き詰めて考えることがゲーム作りの原点になるのでは」と議論を発展させました。
和田は「おもしろさの本質は世界共通。大作ゲームの場合はグラフィックや音楽などで海外に合わせた作り方は必要だと思うが、インディゲームのような小規模なタイトルでは必要ないのでは」と言います。自分自身も国内向け・海外向けにこだわることはなく、ユーザーに楽しんでもらえるものを作るのが一番。大勢の人に楽しんでもらえるのなら、テキストもなくて良いと思うタイプだとのこと。
その上で「自分が作りたい物を作るのがインディ」なので、市場に媚びたようなゲームでは「自分らしさ」が出ないのであれば、自分流にこだわればいい。おもしろいゲームを作ってSNSで発信すれば、そこから広まる可能性があるのが今の世の中なので、無理に宣伝しようとするのではなく、自分のゲームのオーディエンスを探そうとする姿勢が重要だと補足しました。
一方で多くの人が「ゲームを作る」以前のところで立ち止まってしまう現状もあります。これに対してアルヴィンは「言い訳ばかりする人は世の中にたくさんいる。プログラムが分からない、絵が描けないとか・・・。でもゲームを作るのは誰でもできるようになった。Make Game!」とコメントし、会場にエールを送りました。マットも同様に「とりあえず一歩を踏み出すことが大事。目標を作って毎日、寝る前に少しずつ作業を進めるとか」とコメント。海外に展開できないから売れない、だから作らないというのも言い訳にすぎないとして、ゲームを作ることの重要性を指摘しました。
木村は「ヒットしたインディゲームはみな、おもしろい。逆につまらないゲームは売れないで欲しい。ゲーム自体が、そんなものだと思われてしまうから」と言います。もっとも何を「おもしろい」と思うかは人それぞれです。
こうした堂々巡りはクリエイターなら誰もが経験したことがあるはず。自分も何度も何度も何度も何度も、そうした逡巡をいろんな人から、いろんな場所で聞いてきました。それが少人数・小資本のインディゲームであれば、よりリアルな問題として直面せざるを得ないということなのでしょう。この4人がどのようなゲームをリリースするのか、期待したいところです。願わくば幸あれ、ヒットあれ。
(小野憲史)