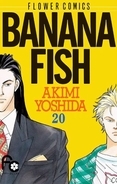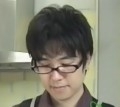なお、お時間に余裕のある方は以前の記事を読んでいただけると、より一層理解しやすくなると思います。
『美味しんぼ』常識はもう古い!? 日本酒ってどう選べばいいの?
■そもそもお酒はブレンドするの?!
今回の事件で「今までは新酒に同酒の古酒などを2〜3%ブレンドしていたが、在庫がなくなったために醸造アルコールや糖類の入った安価な酒を混ぜた」という報道がなされました。そこで、「え?! 新酒なのに古酒を混ぜていたの?!」と思った方もいるでしょう。
お酒をブレンドすることには問題ありません。というか、意外とお酒の世界ではそういう例が多いのです。
例えばウイスキーを見てみましょう。「12年」と書いてあるウイスキーは12年前のウイスキーのみを瓶に詰めて売り出されたものと思いがちです。が、実はそうではありません。
このウイスキーの「12年の味」というのが決まっていて、ブレンダーの人がその味になるよう、さまざまな年のウイスキーをブレンドして、出荷するのです。だから毎年同じ味で、安定して「12年」が発売されるのですね。じゃあ12年というのは嘘なの? というと、これは間違いで、基本的には●年とついたものは、ブレンドしたウイスキーの中で一番新しいものの年数がつけられます。なので、12年と書かれていたら、12年よりも前のものしか使われていない、場合によっては20年とか30年とかもブレンドされているウイスキーになるというわけです。
お酒は発酵物です。発酵が絡むということは、全く同じような条件を整えていても、同じ結果が出るわけではないということでもあります。ましてや、去年の米と今年の米は100%同じものではないのです。実は、毎年同じ銘柄を同じ味に仕上げるのはとても大変なのですね。なので、少しブレンドして味を調整するということはあるのです。
別に話は古酒を混ぜるということに限ったことではありません。例えば「純米酒」を造ったとしましょう。たくさん造るので、仕込みタンクが複数あり、同じお米で同じように発酵させたとします。どんなに注意深く造ったとしても、タンクごとに味がちょっとずつ違っていたりするのですね。そうなると同じ「純米酒」のラベルを貼っても、瓶ごとに味が違うということになってしまう可能性があるので、それらを混ぜて味を調整して出荷したりもするのです。ちなみにBY(醸造年度)表記があるものは仕込みタンク間のみで、違うBYのお酒とのブレンドは無いと考えればいいでしょう。
こういったブレンド技術は蔵の腕の見せ所でもあり、個性でもあります。毎年同じように美味しい、味が変わっていないと感じる秘密は、ここにあったのですね。
■お酒に醸造アルコールを入れるのは良くない?!
醸造アルコールを入れたのが悪いようにも見える報道もありますが、醸造アルコールは日本酒に添加が許可されています。醸造アルコールの原料は基本的に米などの穀類やさとうきび(廃糖蜜)といったデンプン質、糖質の原料を使って酵母で発酵させ、連続式蒸留機で蒸留したものです。化学的に合成された工業用アルコールというわけではありません。
醸造アルコールを入れても、特定名称酒と呼ばれるお酒になります。具体的には「純米」とついていないもの、本醸造酒、特別本醸造酒、吟醸酒、大吟醸酒になります。なので「純米酒」に醸造アルコールを入れるのはアウトになります。
さらに問題になるのは、量でしょうか。特定名称酒では醸造アルコールを添加する量が厳しく制限されています。具体的には、「醸造アルコールについては、アルコール分95パーセント換算で、白米重量の10パーセントを超えないものに限る。」という決まりがあります。この量を超えてしまった場合、特定名称酒を名乗ることができません。
じゃあこれらの決まり事を破ってしまったお酒は日本酒じゃなくなるのでしょうか。そうではありません。特定名称酒ではなくても「普通酒」と呼ばれるカテゴリーの日本酒になるのです。
■普通酒ってなあに?
普通酒は、特定名称酒以外の日本酒です。これが大きなポイントになります。
特定名称酒は原料に米、米麹、醸造アルコールしか使ってはいけません。これ以外のものが加わったお酒は「普通酒」になるのです。
日本酒は米からできているので、基本的には甘いお酒と考えるといいでしょう。米のでんぷんを分解して糖にし、糖をさらにアルコール(と二酸化炭素)にして作られるお酒です。ここでポイントになるのは、糖は甘く、アルコールは辛いということでしょうか。
醸造アルコールをたくさん入れると糖よりもアルコールの比率が高まり、そのお酒は辛くなります。辛くなりすぎたお酒を甘く調整をするために、糖類添加物や調味料を加えることがあるのです。これがチェーンの居酒屋などで「日本酒」を頼んだときに出てくるベタベタした甘さのお酒の正体と言えるでしょう。
ただし、普通酒は先に言ったように、特定名称酒以外の日本酒です。従って、様々な添加物が入っているものもあれば、そうでない造り方をしたお酒もあります。例えば「農産物検査法によって3等以上に格付けされた玄米又はこれに相当する玄米以外の米を使っている。」という条件が特定名称酒にはあるため、等外米(格付けされていないお米)を使った純米のお酒は普通酒になるのです。ここがちょっとややこしいところですね。ベタベタした甘さを避けたければ、ラベルの原材料欄を見て調味料や糖類添加物が入っていないかを確認するといいでしょう。
ちなみに、悪名高い「三増酒」(アルコール添加で3倍に増やしたお酒)は現在ではリキュール扱いになっています。普通酒とは違うので注意が必要です。
普通酒と特定名称酒のシェアは7対3です。普通酒が日本酒全体の7割を占めているのです。今回のお酒も普通酒を混ぜたために糖類が検出されたものがあったとのことで、これが普通酒として売り出されていれば法律上は問題はなかったということですね。
今回の事件は、非常にあってはならないことではあります。でも、一部の報道の仕方では、何でもかんでも混ぜたのが良くないみたいに受け取れるものがあります。そうではなく、特定名称酒に普通酒を混ぜたり、純米酒に醸造アルコールが入っているお酒を混ぜたことが問題なのです。今後はこういう事件が起こらないことを切に願います。
(杉村 啓)