候補作が発表されてからの間、どれだけ同じことを質問されたかわからない。
「『火花』は受賞すると思いますか?」
聞かれるたびに同じことを繰り返してきた。
「火花」の受賞はないと思う。
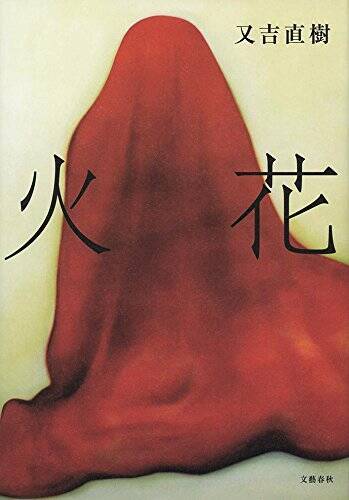
理由はいくつかある。ここ数回、世間で知名度が高くなった作品に授賞した例がないから、というものもそのひとつだ。
第149回、第150回のいとうせいこう(『想像ラジオ』『鼻に挟み撃ち』)、第150回の岩城けい(『さようなら、オレンジ』)などがそうだ。厭らしい言い方だが、すでに十分売れた作品の書き手にさらなる追い銭を遣るだろうか、という疑問が浮かんでくる。候補者のうち、「火花」の又吉直樹と「MとΣ」の内村薫風のみがいかなる新人賞も受賞していない(内村が覆面作家の別名義でなければ)という「文壇に対する身内感のなさ」もある。
新人ゆえのまだ甘い部分
しかしそういうどうでもいい理由は別にしても、又吉直樹にはくれないのではないか、という気がする。
「火花」を私はおもしろく読んだ。これは売れない漫才コンビのボケ担当である徳永(僕)という男が、先輩芸人で同じく売れない漫才コンビを組んでいる神谷と出会い、その才能に一目惚れして弟子入りするところから始まる物語である。つまり芸人小説だ。
読み進めるうちに、〈僕〉には神谷が他の芸人と一線を画しているように見えているということがわかってくる。他の芸人には観客が重要である。
本作の笑いは、もっぱら神谷と〈僕〉の言葉遊びや二人の情けないエピソードから生まれてくる(中盤に、神谷があることを我慢するために〈僕〉に勃起するように命ずる輝かしいエピソードがある)。その部分はたいへん楽しいのだが、又吉の筆致はところどころで甘くなる。「路傍の吐瀉物さえも凍える、この街を行く人々は誰も僕達のことを知らない。僕達も街を行く人のことを誰も知らない」といったうじゃじゃけた文章が章の切れ目に置かれたりする。新人ゆえのまだ甘い部分だ。話題作となっただけに、選考委員はそうした未成熟な部分を見逃さないのではないかという気がする。それが本作が賞を逸するだろうという予想のいちばん大きな理由だ。
「埋め合わせ」もありうる
では何が獲るだろうか、ということだが、私は前回に続いて二度目の候補となった高橋弘希「朝顔の日」ではないかと思う。高橋は前回「指の骨」という南方戦線の負傷者を主人公にした作品で候補になった。私は十分授賞に値する作品だと思っていたのだが、落選した。選評を読むと、過去の戦争と現在をつなぐものが稀薄だという意見があったようである。「朝顔の日」は、同じように先の大戦を描いた作品だが(作中に1941年12月8日に関する記述が出てくる)、戦争そのものの記述は後退し、代わりに入院した妻とそれを見舞う夫という普遍的な情景が前面に出てきている。
作中にそうは書かれていないが、妻の病名は結核である。ストレプトマイシン投薬が一般的になる以前、日本では結核は死病だった。妻が漂わせている死の予兆が、太平洋戦争の歴史を暗示させる形で描かれているのだ。戦争の悲劇を直接書かず、一回肉親愛の中を経由させる。それこそが前回の「宿題」に対する高橋の回答なのではないか。前回の残念があるだけに、今回は「埋め合わせ」もありうる、というのが予想の理由である。
候補作のうち、ここのところ好調な新潮新人賞受賞者が2人いる。高橋と、今回が初候補となる滝口悠生だ。
ではどちらに意味があるか、と言えば「ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス」のほうだろう。「MとΣ」は三題噺的な着眼点のおもしろさはあるのだが、それ以上のものはないと思う。滝口の作品は現代史上に意味の大きな2つのポイントに語り手の個人的な体験をきちんと沿わせ、しかもそこに年上の女性への思慕という魅力的なエッセンスを振り撒いている。時制が攪乱される原理にジミ・ヘンドリクスの革命的なギター奏法を重ねている点も綺麗なやり方だと思う。よって私は「ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス」を本命「朝顔の日」の対抗に挙げたいと思う。
ああ、こういう編集者がいるのだろうな
他2作は島本理生「夏の裁断」と羽田圭介「スクラップ・アンド・ビルド」だ。候補となるのは共に4回目である。
「夏の裁断」の裁断とは本の自炊作業のことを指している。小説家の萱野千紘(私)がその作業をしながら、柴田という風変わりな編集者についての記憶をたどり、それにつれて彼女の男性観を形作った過去についても言及が行われていく。この柴田という編集者が、普段は「萱野さん/僕」なのが要所で「おまえ/オレ」に呼称が変わるというのが本当にいやらしく、ああ、こういう編集者がいるのだろうな、と怖気をふるいながらもおもしろく読み終えた(萱野千紘には、男性に対して臆病になるだけの理由があるとされるが、その理由は特に意外なものでもない)。
「スクラップ・アンド・ビルド」は、「他の人間とは共有できない目的のために一人奮闘する男」という羽田小説ではおなじみの人物が主人公となる作品だ。前回の「メタモルフォシス」ではマゾヒズムがその行動原理であり、非常に突飛でおもしろかったのだが、今回は高齢者となって生きる意味がない(と主人公には見える)祖父に安楽死を与えるという物語で、無職で家にいる主人公がやたらと下半身の鍛錬をする個所が可笑しい。おおいに笑わせてもらってありがたかったが、うーん、それだけでは芥川賞は難しいよね。
希望をこめて本命
直木賞候補6作のうちでは、東山彰良『流』がもっともおもしろかった。日本国内だけではなく、世界の市場で通用する小説を候補作から1つ選べ、と言われたら迷わず本書を挙げるだろう。自身が台湾出身で幼いころ日本に移住してきたというプロフィールを東山は明らかにしているが、幼少期を過した台湾を主舞台とする小説である。台湾の現代史は日本の植民地支配と国共内戦という2つの大きな事件によって形成されている。冒頭で語られる殺人事件の謎解きを通じて中華民国という国の成り立ちについての再認識が行われるという、理想的な歴史叙述が行われる。しかもそれは作品を支えている柱の1本にすぎず、複数あるうちのもう1本の太い柱は、17歳から26歳に至る主人公の青春物語である。これがかなりぼんくらで、おまけに野放図で、ところどころ切ない。多面体の輝きを放つ素敵な小説だ。
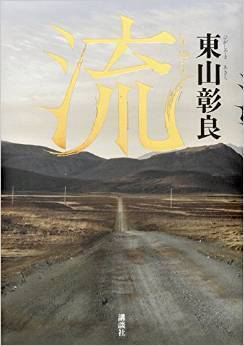
今回が初候補となる作家が東山の他に2人いる。『若冲』の澤田瞳子と『東京帝大叡古教授』の門井慶喜である。『若冲』は奇想の画家として名高い伊藤若冲の生涯を描いた作品で、連作形式をとっている。それぞれの絵について、作者・若冲の心理分析が行われ、その集合体が一つの肖像となるように計算された作品だ。『東京帝大叡古教授』のほうはウンベルト・エーコを思わせる知の巨人を明治時代の東京帝大に登場させるという試みの歴史推理で、同じく連作形式で書かれている。こちらは通読すると現代に通じる問題意識が浮上してくる仕組みである。つまりカリカチュアなのだが、いかにも虚構らしい内容で重要な現代の問題を扱うことに拒絶反応を示す読者もいそうな気がする。
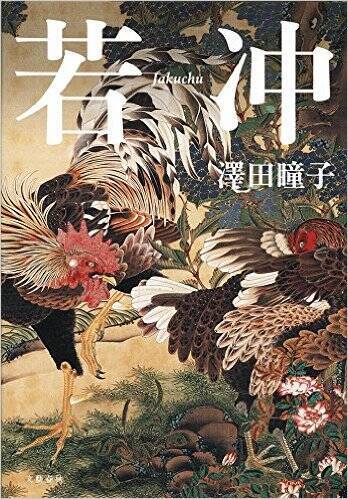
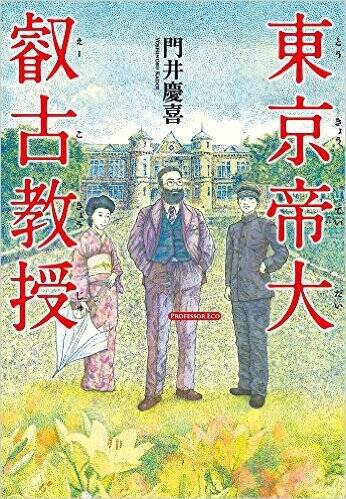
は新傾向の作品
候補作中最多となるのが『アンタッチャブル』の馳星周で、6回目である。前回が138回なので、7年半間が空いたことになる。馳の作品では警察小説の定型を破り、犯罪小説との完全な融合を企てた『ブルー・ローズ』という大傑作が候補にもならずに見過ごされており、他にも代表作はことごとく無視されてきている。つまり直木賞とは為さぬ仲のような作家なのだが、今回の『アンタッチャブル』は、馳の作品としては新傾向の作品である。
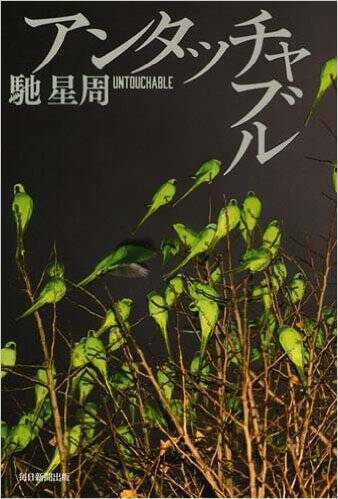
馳に次ぐのが『ナイルパーチの女子会』の柚木麻子で、これで3度目になる。ナイルパーチというのは魚類の名前で、この魚を不用意に放流すると、その水域の生態系が壊されてしまうほどの凶暴性を持っているという。柚木は2人のヒロインを準備し、どちらかがナイルパーチとなって相手の生態系を怖しにかかるという物語を展開する。一般市民がブロガーとしてスター並みの脚光を浴びる共感優先社会の奇妙さ、「女子会」という物の言いように顕著な、男性ではそんなことはないのに、女性のみが何かにつけて特別扱いをされるような非対称なジェンダーのありようなどが、この関係に肉付けをする建築材として使われるのである。
たいへんおもしろく、予断を許さない展開のダイナミックさがある。登場人物が自分の行動原理を逐一説明してくれるのは「わかりやすさ」が尊ばれる現代の風潮を考慮してのものだとしても、その説明のために小説が、やけにおさまりのいいところに着地してしまうのはもったいない瑕だと私は考える。『本屋さんのダイアナ』にしてもそうだったが、無理にいい話にしなくてもいいのに。

いわゆる「いい話」
最後の1作、2度目の候補となる『永い言い訳』に一応対抗マークをつけておきたい。これも先の読めない展開をする小説なのでストーリーはすべて省くが、曖昧な書き方をすると、他人とはまったく異なる感情のありようをした男性主人公が、それゆえに周囲から浮き上がり、自分なりの落ち着き方をしていくまでの話ということになる。その過程では心理学でいうところの代償としか思えない行為に走ることがあり、人間関係に奇妙な平衡状態が訪れる。いわゆる「いい話」になるのだ。そこからの変転のさせ方が非情でよく、評価する所以である。前回候補になった『ゆれる』も評価は悪くなかったようだし、今回はいいところまで行くんじゃないのかな。

(杉江松恋)






























