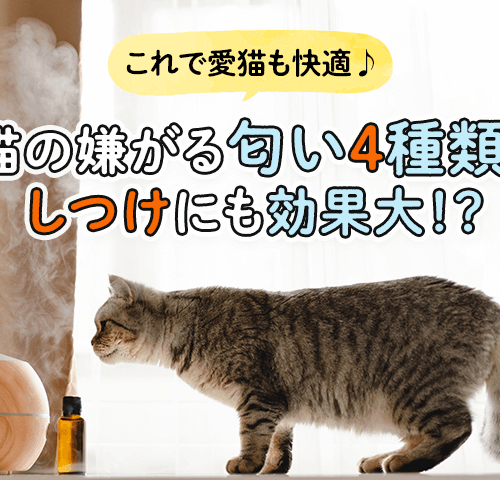近頃どうも気になる猫の匂い!いくら愛猫がかわいくても、猫がいることが原因で発生する悪臭は不快なものです。
家族が耐えられなくなる前に、また来客に指摘される前にどうにか解決したいものですよね。
猫を飼っている以上、匂いのない環境にはもう戻れないの?いえいえ、そんなことはありません。
臭いトイレのニオイや部屋全体に漂う匂いを消して、人の鼻に快適な家を取り戻しましょう!
猫の匂い対策!強烈なトイレの匂いを消す方法なんてあるの?

匂いの発生源として可能性が高いのは、なんといってもトイレです。猫の排泄物が入る場所ですからね。
それに猫のウンチやおしっこの匂いは結構強烈!!猫はタンパク質主体の食事をするので、排泄物にもタンパク質が含まれています。
これが分解される時に強い匂いを出してしまうんです。
では、猫のトイレのイヤな匂いを消す対策方法を順に見ていきましょう。
対策法1:適切な方法でトイレをケアする
猫のトイレが臭いのなら、排泄物の処理や掃除の仕方を見直してみましょう。ポイントは以下の3つです。
1日に1回、排泄物の処理をする
排泄物の処理を行うのは、少なくとも1日に1回!
当たり前ですが、ウンチやおしっこが溜まれば溜まるほど匂いの元は多くなります。猫が自分で猫砂をかけるから、といっても匂いの拡散を完全に断ち切れるわけではありません。
それに、トイレの汚れを猫が嫌がれば、別のどこかで排泄してしまう可能性も出てきます。
1ヶ月に1回、猫砂を入れ替える
また、トイレに入れている猫砂は、1ヶ月程度ですべて入れ替えるようにしましょう。同じ猫砂をずっと使っていると、吸収力が落ちたり汚れたりしてきます。
1ヶ月に1回、トイレ自体を洗う
猫砂を入れ替えるついでに、トイレ自体を洗うのを習慣とするとよいですね。洗ってトイレ本体に付着している雑菌を落とせると、匂いの発生も抑えられます。
対策法2:トイレ用品をグレードアップする
上のようなケアを既に実践しているのに匂いがする。あるいは仕事や家庭の事情でなかなか実践できない、といった人もいるでしょう。
そんな場合は、思い切ってトイレ用品をグレードアップするのも1つの方法ですよ。おすすめ用品は次の3つです。
消臭効果に優れた猫砂
いつも使っている猫砂の種類を変えてみましょう。猫の室内飼いが主流となっている現在、猫砂にはさまざまな原料を使って工夫された商品が販売されています。
軽い、トイレに流せる、安全性の高さなどメリットはそれぞれ違うので、中でも消臭力に期待できる猫砂を選んでみてください。
カバー付きの猫トイレ
あるいは、トイレ本体のグレードアップを考えましょう。現在オープンタイプのトイレを使っているなら、カバー付きのトイレに替えるだけでも匂いの広がりを抑えられます。
引き出し付きのシステムトイレ

でも、個人的には一押しはこちらの写真のようなシステムトイレです!
普通のトイレと同じように見えて、下側にシートを敷く引き出しがついているという構造。おしっこが、すのこをすり抜けてシートに吸収されるのであまり匂いません。
我が家では猫砂代わりに木製ペレットを使用しています。匂いの防止もコスパも抜群です。見た目の印象以上に優れものと、実感していますよ♪
対策法3:トイレ回りの環境を見直す
猫のトイレ関係でできる対策はまだあります。それはトイレ回りの環境を見直すこと。具体的には以下のような方法が取れます。
適宜空気の入れ替えをする
帰宅後に窓を開けたり換気扇を回したり、意識して空気の入れ替えをするようにしましょう。単純ですが、新しい空気が入ってくれば滞っていた匂いも消えやすくなります。
トイレの位置を移動させる
また、その効果を上げるためには、空気の流れやすい位置にトイレを配置するのがポイントです。室内の空気の流れを確認した上で、よい位置にトイレを移動させてみましょう。
場所が変わったことを愛猫に教えるのも忘れないようにしてくださいね!
消臭アイテムを利用する
空気の入れ替えやトイレの移動がままならない場合は、消臭アイテムをうまく利用してみてください。小型の脱臭機なら、トイレ横でも場所を取らずに活躍してくれます。
多少匂いが気になる程度なら消臭スプレーでも対応できますよ。
家が猫臭い時に出来る匂い対策とは?

家全体に猫臭い匂いがこもっている時、発生源はトイレとは限りません。トイレ以外の匂いの元は大きく分けて2つ!食べ残しフードと尿スプレーです。
原因を突き止めて、それぞれ匂いを消すには次のような対策を取りましょう。
対策法1:フードの片付けはすみやかにする
匂いの元がフード周辺とはっきりしたら、対策法は1つです。猫の食事タイムが終わったら、すみやかに片付けるようにしましょう。例え食べ残していても、です。
猫が口をつけたフードや容器の汚れをそのままにしていると時間が経つごとに雑菌が繁殖し、匂いが発生することとなってしまいます。
食べ残しフードを処分し、餌や水の容器をそのつど洗って清潔を保ちます。
対策法2:スプレーには熱湯とアルコールが効果的
トイレでもフードでもなく壁や床が匂っている場合は、猫がスプレー行為をしている可能性が高いです。
スプレー行為は、主に発情期のオス猫がマーキングを目的に行うもの。この行為で縄張りの主張やメス猫へのアピールをしているんですね。
マーキングの目印は匂いなので、当然強い匂いがします。
それに、この匂いをそのままにしておくと一時的な問題だけに収まらないんです。匂いがする場所には猫が再びスプレーをする可能性があります。
もし現場を目撃するか匂いで場所が特定できるのなら、できるだけ早く雑巾などで拭き取りましょう。
そして、スプレーがかかった場所の素材ごとに次のような方法を組み合わせて対処します。
熱湯をかける
匂いのする部分に沸かしたお湯をかけます。その後温度に気をつけながら、布で拭き取りましょう。鼻につんとするアンモニアは、熱湯の力で分解されます。
熱で影響を受けない素材、洗濯しにくい素材に適した方法です。
酸性の液体で中和させる
スプレーの尿はアルカリ性なので、酸性の液体で中和させる方法が有効です。
自宅に常備しているものであれば、調味料の酢。あるいはクエン酸でもOKです。水で薄めたものをスプレー容器に入れて、吹き付けます。その後もう一度雑巾で拭き取ります。
消毒用アルコールを使う
更に消毒用アルコールを使っておけば、心強いです。アルコールの殺菌力で匂いの元となる雑菌に対処できます。
消毒用アルコールは、匂い対策以外のシーンにも活躍してくれるのでおすすめですよ。
我が家のオス猫は去勢済なのでスプレーすることはありませんが、たまにある吐き戻し後の掃除に使っています。
根本的な解決は去勢手術
実は早くから去勢したオス猫はスプレーをあまりしません。これが根本的な解決法です。
ただ、手術時期が遅れて発情期を迎えてしまうと、スプレー行為が収まらないケースもあります。なるべく早めに検討してみてくださいね。
対策法3:空気清浄機を稼働させる
原因が特定できず漠然と匂いが気になるのなら、空気清浄機に頼るのもよい方法です。留守が多い家庭や寒い季節だと、常に窓を開けて換気できるわけではありませんからね。
脱臭機能が優れたものやペット対応のものなど、さまざまな商品が揃っています。部屋の広さや予算に合わせて選んでみてください。
ペット対応のものは匂いだけでなく、抜け毛の対策にも効果的ですよ。
もし猫ちゃんが臭い時の対処方法は?

臭い匂いを辿っていくと、発しているのはなんと猫そのもの!そんな場合もあります。
ですが、ある程度猫との暮らしが長い飼い主さんなら、おかしいなと感じるはず。
狩猟する動物である猫は、他者に存在を気づかれにくいようグルーミングで匂いを消すのが習性です。
つまり、猫の体の匂いはある種のサイン。その裏にはなんらかの異変や病気が隠れている可能性があるんです。
匂いのする部分は大きく分けて3つ。口の辺り、おしりの辺り、そのほかです。
口が匂う場合は病気が潜んでいる!?
猫の口の辺りが匂う場合、このような原因が考えられます。
この中で飼い主さんが対処できるのは、明らかに口の中の食べかすが原因である場合のみ。多くは歯磨き用品の使用やドライフード中心の食事に変更することで解消できるでしょう。
そうでない場合は、1度病院で診てもらってください。可能性のある異変は、軽いものから重いものまでさまざま。
一見口の中のトラブルだけに思えても、ほかの病気が潜んでいることもあるのです。病気があれば根本的な治療をしてもらうことが大事です。
おしりが匂う原因は排泄物か肛門腺
匂うのが猫のおしりの辺りであれば、主な原因は2つ。排泄物か肛門腺です。
おしりが排泄物で汚れている
もしおしり周りが排泄物で汚れているなら、濡らしたティッシュなどで拭き取ってあげてください。
そして、うんちがいつもと違っていないか確認を!もし下痢をしているようなら、病院に連れていきましょう。
肛門腺の分泌液が溜まっている
猫の肛門腺からの分泌液は通常であればうんちと一緒に出て、その匂いは相手の識別やマーキングなどに役立っています。
肛門腺が異常に匂う場合は、炎症や化膿などのトラブル、あるいは体質的につまりやすい猫です。どちらも動物病院で対処してもらえるので、受診しておくと安心です。
単に分泌液がつまっているのであれば、対処方法は人の手で絞り出すこと。定期的に絞ることで匂いやトラブルを避けられるため、自分で絞るやり方を覚えておくとよいでしょう。
- 尻尾を持ち上げて、猫の肛門腺の位置を確認。肛門から左右に斜め下2ヵ所です。
- 肛門腺の2ヵ所をティッシュで覆い、その上から指で押します。
- 肛門に向かって、1~3回押し上げるようにしましょう。
- 肛門から出た分泌液をティッシュでふき取ります。
中で分泌液が溜まって固まっている場合は、簡単に取れないこともあります。また、テキパキ進めないと、デリケートな部分に触られた猫が激怒することも!
そうした時は、無理せず動物病院やトリミング施設に頼りましょう。
そのほかの匂いにも体調不良が関係している
口とおしり部分以外が匂う場合に考えられるのは、次の3つです。
- 皮膚炎
- 口臭の移り香
- グルーミング不足
どれも猫のどこかに異変があることを示しているので、早めに獣医さんに診てもらいましょう。
皮膚炎が原因であれば、その部分が匂いの直接の発生源です。
少しわかりにくいのが、口臭のある舌でグルーミングを行ったために体全体が臭くなってしまった場合。それに、体調不良でグルーミング自体ができない場合です。
猫の様子は飼い主さんにしか気づけないこともあります。何かおかしな点があれば、病院の受診時に伝えるようにしてください。
幸せな猫との生活も、不快な匂いが漂えば笑顔でいられません。すみやかに適切な対策法を取り、イヤな匂いを消したいものです。
匂いの発生源は、トイレ、室内全体、猫そのものの3つに分けられます。トイレの匂いはケア方法や環境の見直し、室内の匂いは飼い主さんの工夫次第で消すことが可能です。
ただ匂いの原因が猫そのものにある場合は、体調不良を疑う必要があります。匂いの悩みを一刻も早く解消して、また笑顔で猫と暮らしていきたいですね。
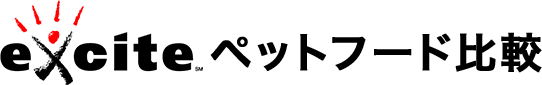

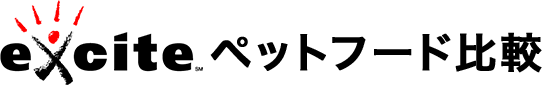


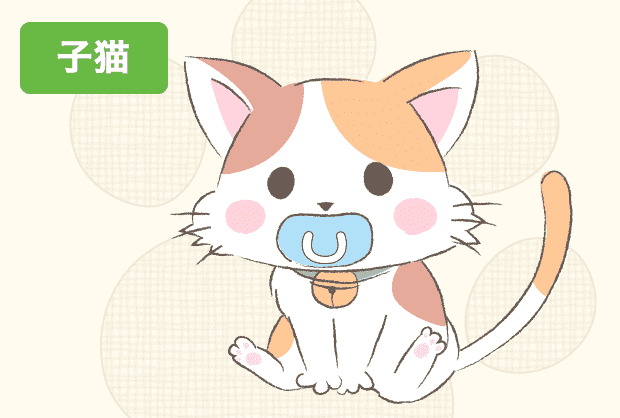
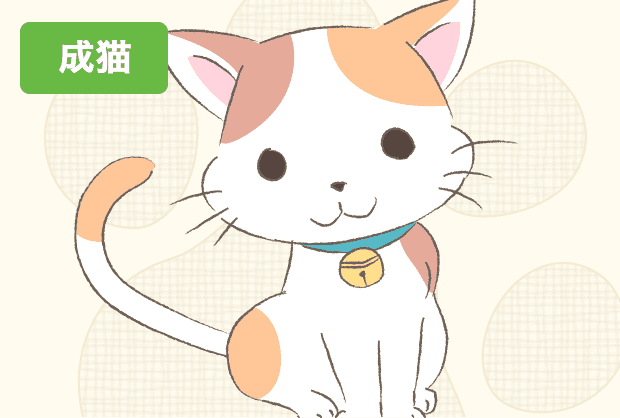
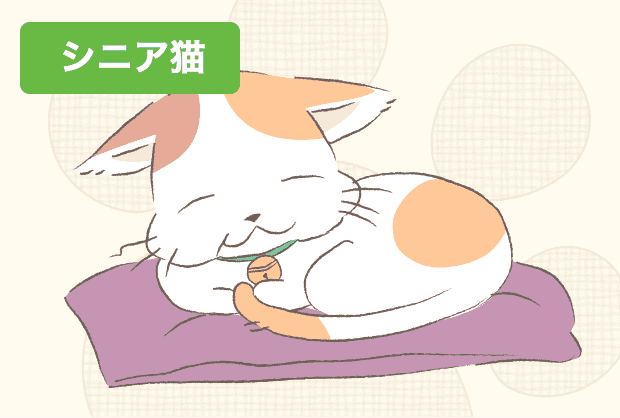
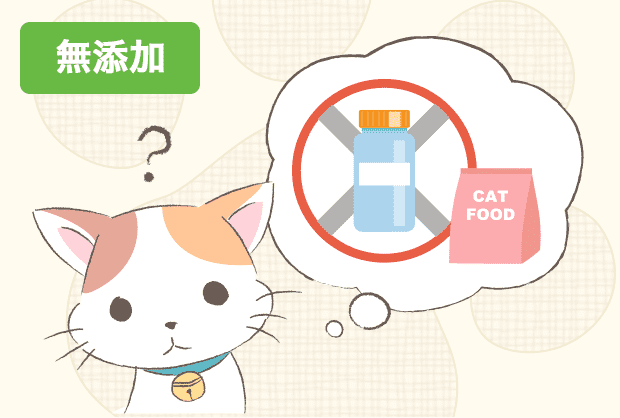
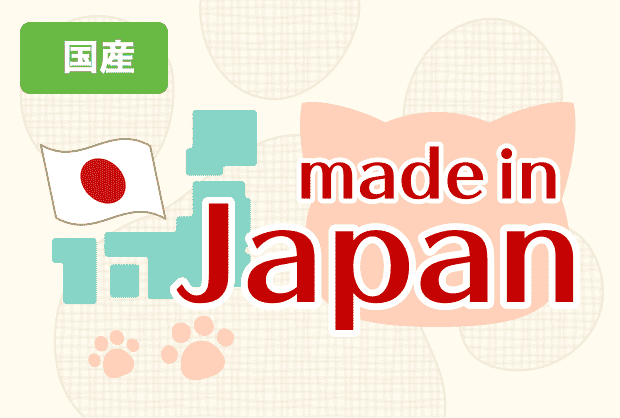
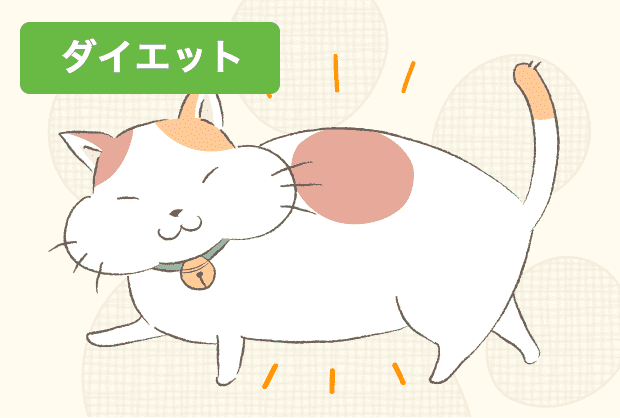
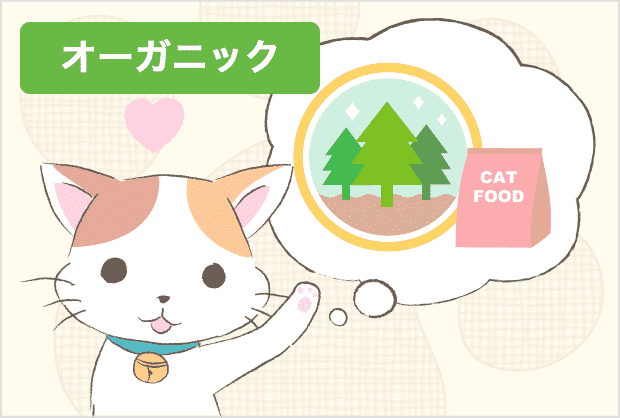
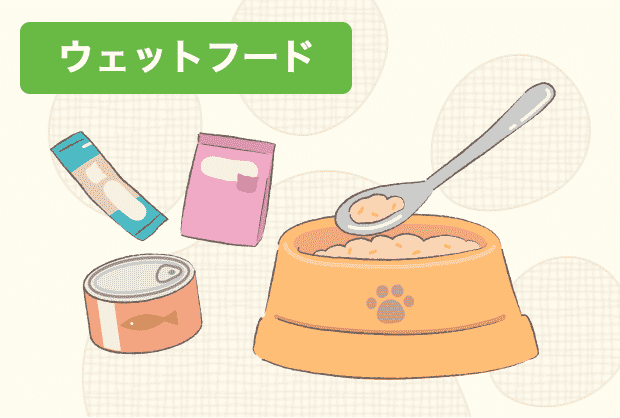


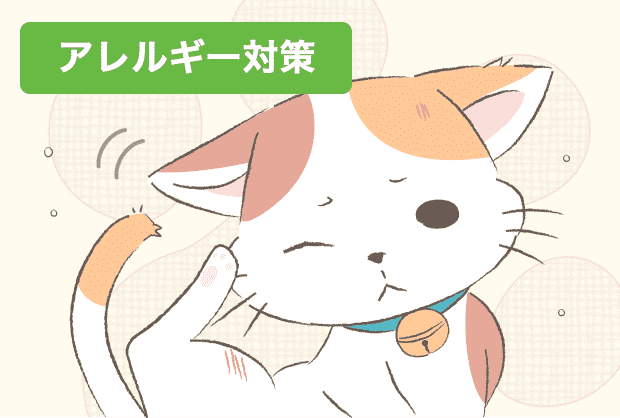
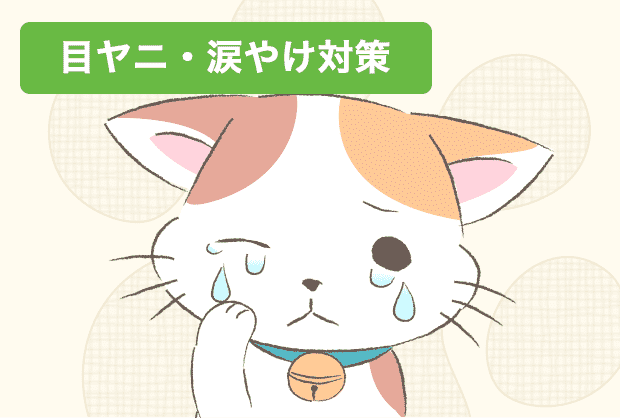
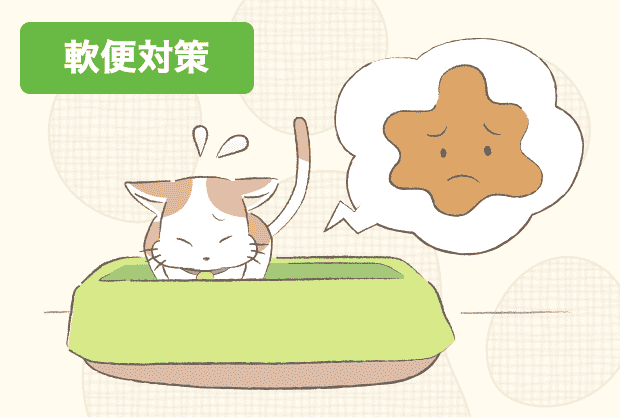
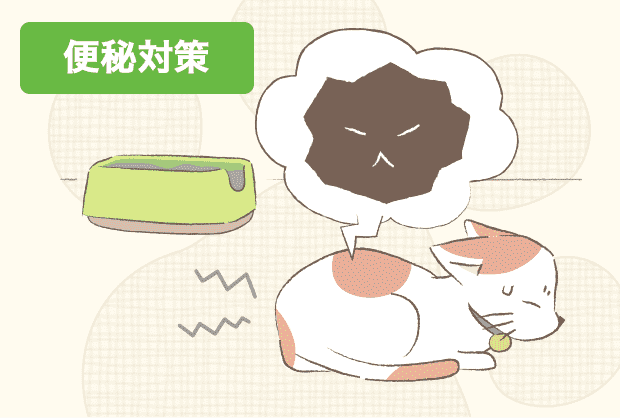
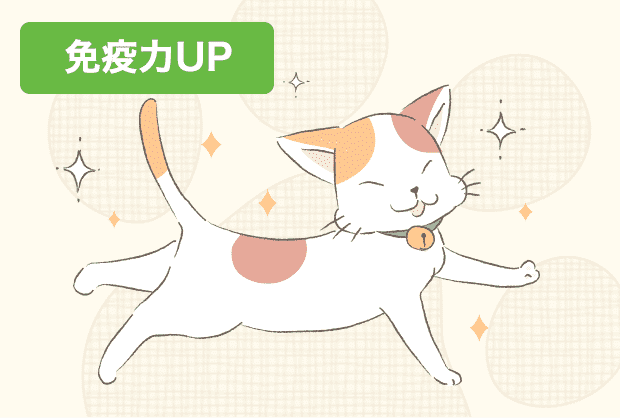
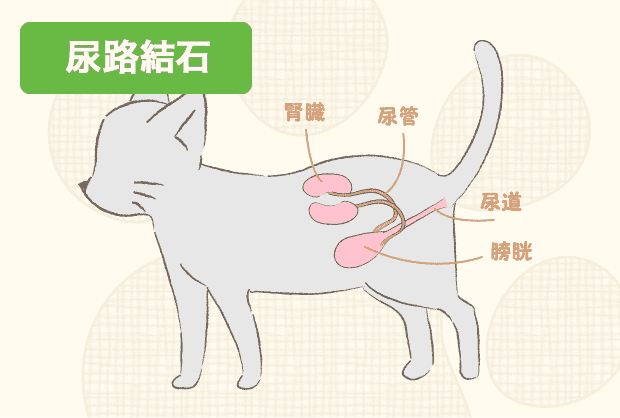
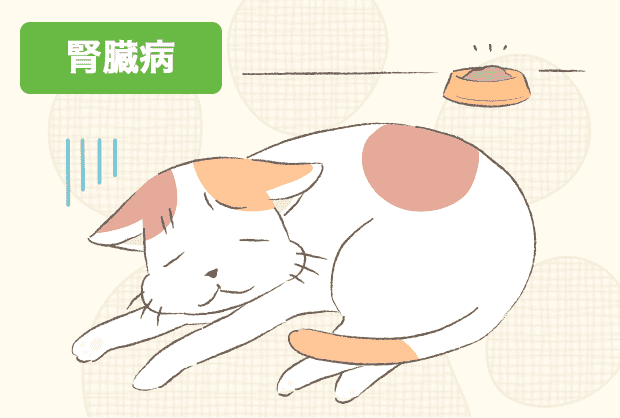
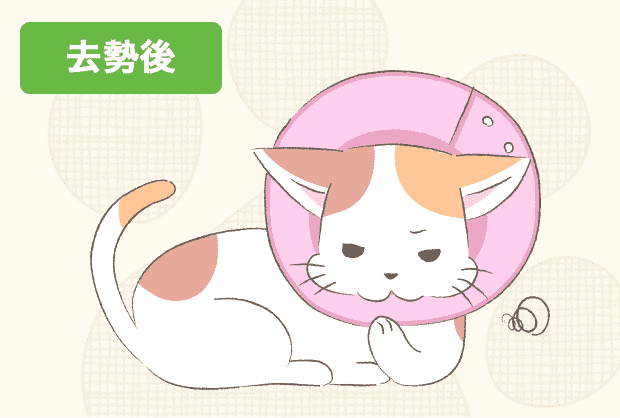
 最新記事一覧
最新記事一覧